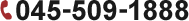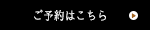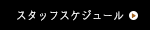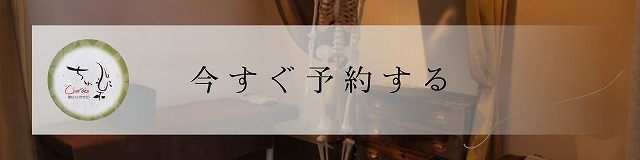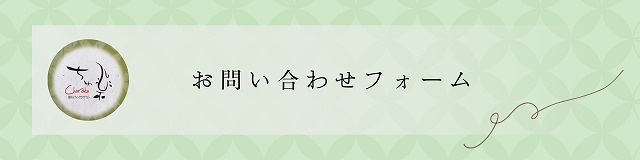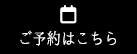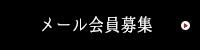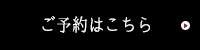カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2026年1月 (15)
- 2025年12月 (26)
- 2025年11月 (29)
- 2025年10月 (31)
- 2025年9月 (30)
- 2025年8月 (25)
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (3)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (3)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (6)
- 2024年3月 (7)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (5)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (3)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (5)
- 2023年5月 (8)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (10)
- 2023年2月 (10)
- 2023年1月 (27)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (2)
- 2022年7月 (3)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (5)
- 2021年4月 (4)
- 2021年3月 (10)
- 2021年2月 (7)
- 2021年1月 (5)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (6)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (9)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (3)
- 2020年5月 (4)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (3)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (7)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (5)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (5)
- 2019年7月 (8)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (9)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (4)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (8)
- 2018年9月 (3)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (7)
- 2018年3月 (6)
- 2018年2月 (9)
- 2018年1月 (8)
- 2017年12月 (12)
- 2017年11月 (9)
- 2017年10月 (13)
- 2017年9月 (15)
- 2017年8月 (19)
- 2017年7月 (12)
- 2017年6月 (16)
- 2017年5月 (8)
- 2017年4月 (20)
- 2017年3月 (14)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (11)
- 2016年12月 (6)
- 2016年11月 (7)
- 2016年10月 (9)
- 2016年9月 (5)
- 2016年8月 (4)
- 2016年7月 (8)
- 2016年6月 (6)
- 2016年5月 (16)
- 2016年4月 (9)
- 2016年3月 (10)
- 2016年2月 (10)
- 2016年1月 (8)
- 2015年12月 (7)
- 2015年11月 (10)
- 2015年10月 (13)
- 2015年9月 (8)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (15)
- 2015年6月 (17)
- 2015年5月 (16)
- 2015年4月 (20)
- 2015年3月 (18)
- 2015年2月 (14)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (3)
- 2014年11月 (9)
- 2014年10月 (9)
- 2014年9月 (8)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (13)
- 2014年5月 (11)
- 2014年4月 (12)
- 2014年3月 (5)
- 2014年2月 (7)
- 2014年1月 (10)
- 2013年12月 (6)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (6)
- 2013年9月 (7)
- 2013年8月 (5)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (8)
- 2013年5月 (5)
- 2013年4月 (6)
- 2013年3月 (4)
最近のエントリー
スタッフブログ 6ページ目
11月に多発する"ぎっくり腰" ― その理由と、発症を防ぐためにできること

「急に腰が抜けたように痛む」「前にかがんだ瞬間、動けなくなった」
そんな ぎっくり腰(急性腰痛) が、毎年11月に多発するのをご存じでしょうか。
実はぎっくり腰は“季節性”が強く、特に 気温変化が急激な11月 に来店が増える傾向があります。
ちゅ楽でも、毎年この時期になると「腰がギクッと…」という相談が連続します。
今回は、なぜ11月にぎっくり腰が増えるのか、そして再発予防のポイントや、
ちゅ楽でできるケアについて専門的にお伝えします。
1. 11月にぎっくり腰が多発する理由
ぎっくり腰の主な引き金は、
筋膜・筋肉の冷え、血流低下、姿勢ストレスの蓄積、疲労の溜め込み
の4つです。
特に11月は、
-
朝晩の冷え込みが急に強くなる
-
自律神経が乱れやすい
-
冬に向かって血流が低下
-
冷えにより筋肉が硬くなる
といった状況が重なり、筋肉・靭帯・関節に負担が集中します。
さらに、この季節は 「寒い → 肩がすくむ → 背中が丸くなる → 腰に負担」 という姿勢サイクルが起きやすく、
ちょっとした動作(洗顔・前屈・荷物を取る・くしゃみ)で発症することが非常に多くなります。
2. ぎっくり腰は“急に起きる”わけではない
ぎっくり腰は突発的に起きると思われがちですが、実際は
「限界まで溜まった疲労の最後の一押し」 が原因です。
腰回りは日常生活で酷使される場所。
特に11月は疲労・冷え・ストレスが同時に強まるため、
-
筋膜の滑走不良
-
関節の可動域低下
-
神経の緊張
-
姿勢の乱れ
が“見えないストレス”として積み重なり、最後にギクッと崩れてしまいます。
3. 発症してしまった場合のNG行動
ぎっくり腰になった直後は、以下の行動は悪化させます。
-
無理に伸ばす
-
お風呂で温める
-
もみほぐす
-
コルセットでガチガチに締める
急性期は炎症が強いため、過度な刺激を加えると痛みが長びくことがあります。
4. 早期改善に必要なのは「筋膜と神経」のアプローチ
ちゅ楽で行うぎっくり腰ケアは、
筋膜、関節、神経の3つの要素を同時に整える ことを重要視しています。
✔ 筋膜リリース
硬くなった腰・お尻・背中・太ももの筋膜をゆるめ、負担を減らします。
✔ 関節の可動域改善
腰だけでなく、股関節・胸椎・骨盤の動きを回復し、動作痛を軽減。
✔ 神経のリラックス
痛みで過敏になった神経を落ち着かせるアプローチ。
✔ 必要に応じてインディバ
深部の血流・炎症・回復力を高める高周波ケアで、痛みの回復スピードをサポートします。
特にインディバは、急性期の痛み軽減においても非常に相性が良く、
「動きやすくなった」「痛みが半分以下になった」
という声も多くいただいています。
5. 再発予防で最重要なのは“腰以外の改善”
ぎっくり腰は腰だけの問題ではありません。
大半は
-
太ももの硬さ
-
お尻の筋肉の張り
-
背中の丸まり
-
股関節の動きの悪さ
-
呼吸の浅さ
-
寒さによる緊張
が複合的に絡んでいます。
そのため、腰だけをケアしても再発を繰り返します。
ちゅ楽のリリース整体では全身のつながりを見ながら調整を行い、
「腰に負担が戻りにくい体」 を目指します。
6. 11月は“ぎっくり腰予防月”と捉えるのが正解
以下に当店のお客様が実践して効果を感じる予防法をご紹介します。
-
寒い日の朝は特に腰を急に曲げない
-
くしゃみは壁に手をついてする
-
湯船でしっかり温める
-
30分に一度、軽く背中を伸ばす
-
インディバや整体で筋膜を整えておく
冬に入る前にケアをしておくことで、ぎっくり腰のリスクが大きく減ります。
7. 今つらい方・予防したい方へ
毎年11月〜1月は、ぎっくり腰の相談が一年で最も増える時期です。
「まだ大丈夫」と思っている方ほど、負担を溜めているケースが多いもの。
-
腰の張りが取れない
-
前屈・起き上がりがつらい
-
朝の一歩が重い
-
急にギクッときそうで不安
そんな方は早めのケアをおすすめします。
ちゅ楽では、あなたの腰の状態・生活習慣・姿勢の癖を見ながら、
再発しないためのケア を行っています。
痛みが出てからでも、予防でも、どちらも大歓迎です。
11月の“腰トラブルの波”に飲まれないよう、ぜひ一度ご相談ください。
(ちゅ楽)
2025年11月20日 07:10





【よもぎ蒸しを探している方へ】

本当に改善したいなら“深部から温める”温活を
― ちゅ楽のインディバで叶う根本からの温めケア
「よもぎ蒸しで温まりたい」「体を芯から温めたい」「冷えをなんとかしたい」
そんな声が増えるのが、秋から冬、そして春先にかけてです。
特に女性は、冷え・むくみ・肩こり・生理痛・自律神経の乱れといった問題を抱えやすく、温活への関心が非常に高まっています。
よもぎ蒸しは、座浴で下半身を中心に温める伝統的な養生法として人気があります。
しかし、最近はこんな疑問を持つ方も増えています。
-
よもぎ蒸しで温まっても、すぐに冷えてしまう
-
汗はかいたけれど、体の深いところが温まった感じがしない
-
温めても生理痛や内臓の冷えが改善しない
-
冷え疲労が年々ひどくなってきた
-
温活を続けているのに、代謝が落ちている気がする
もしあなたが「もっと根本から温まりたい」「長続きする温活がしたい」と感じているなら、
ちゅ楽が提供するインディバ温熱ケアが大きな助けになります。
■ よもぎ蒸しとの違い
― “深部体温”を上げられるかどうかが鍵
よもぎ蒸しは、皮膚表面~皮下の浅い部分を温めるのが得意です。
一方でインディバは、高周波(448kHz)によって 体内で熱を作り出す「ジュール熱」 を発生させ、
筋肉・内臓・血管・神経などの身体の深部に直接アプローチできます。
これは、よもぎ蒸しやサウナ、岩盤浴では到達できない領域です。
● 深部体温が上がるとどうなる?
1℃上がると、
-
代謝:約12%向上
-
免疫力:最大30%向上
-
内臓機能:活性化
-
自律神経:安定しやすくなる
つまり、表面だけ温まるのではなく、身体そのものが“温まりやすい体質”に変わるということです。
「体を温めてもすぐ冷える」
「手足の冷えが慢性化している」
という方は、深部体温が下がっている可能性があります。
ここに、インディバの強みが光ります。
■ インディバを温活に選ぶべき理由
① 内臓の冷えにアプローチできる
よもぎ蒸しで汗はかけても、お腹の奥にある腸・子宮・肝臓などの“内臓そのもの”を温めるのは困難です。
インディバは内臓周囲まで熱が届き、特に女性が抱えやすい
-
生理痛
-
PMS
-
冷え性
-
便秘
-
むくみ
などの根本改善に役立ちます。
② 自律神経まで整う
深部が温まることで副交感神経が優位になり、
-
眠りやすくなる
-
胃腸の動きがよくなる
-
不安やイライラの軽減
など「精神面」の回復も早くなります。
③ 冷え+肩こり・腰痛も同時に改善
血流が改善するため、慢性的な痛みにも効果的。
よもぎ蒸しでは難しい 筋肉の深部のコリ にアプローチできます。
④ 効果が長続きする
施術後、
「足先までずっと温かい」
「次の日がラク」
と驚かれる理由は、細胞そのものの代謝が高まっているからです。
■ 冷えの本当の原因は
「筋肉不足」でも「血流」でもない
冷えの原因は“熱を作る力の低下”です。
40代以降になると
-
筋肉量の低下
-
ホルモンバランスの変化
-
自律神経の乱れ
により、体が熱を作れなくなります。
つまり、
体質そのものを変えていく温活でなければ、根本改善は難しい
ということです。
インディバはこの「熱を生み出す力」を内側から高められるため、体質改善に最適なのです。
■ ちゅ楽のインディバは“温め+施術”で効果を倍増
ちゅ楽では、インディバをただ当てるだけではありません。
経験20年以上の院長が、あなたの体の冷え方や筋肉の状態、生活習慣から 最適な施術の順番と組み合わせ を組み立てます。
例)
-
内臓の冷えが強い方 → お腹+骨盤周囲
-
肩こり・首こりがつらい方 → 胸・肩・肩甲骨周囲
-
全身がだるい方 → 背中全体+脚
-
不眠・自律神経の乱れ → 頭・首まわり
同じインディバでも“当て方”が変わるだけで、効果が大きく変わります。
■ よもぎ蒸しを探している方に、
なぜインディバを勧めるのか?
答えは簡単です。
あなたが本当に求めているのは「表面的な温まり」ではなく「体質が変わる温活」だからです。
-
手足だけでなく、お腹や腰の奥が冷える
-
代謝が落ちた
-
眠りが浅い
-
疲れが取れない
-
生理痛がつらい
-
自律神経が乱れやすい
これらは、深部体温低下と内臓冷えのサイン。
よもぎ蒸しで満足できない理由はそこにあります。
インディバなら、“温まりやすい身体”へ変わるサポートができます。
■ 温活のゴールは「冷えない体づくり」
体を温める行為は手段であって、目的ではありません。
目的は、
冷えない・疲れない・整った身体をつくること。
インディバはそのための最短距離です。
冷えで悩んでいる方、よもぎ蒸しでは物足りなさを感じている方は、ぜひ一度インディバをお試しください。
あなたの体が本来持っている「温まる力」が引き出され、毎日がぐっとラクになります。
(ちゅ楽)
2025年11月19日 07:51





【ヘッドマッサージを探している方へ】

「脳疲労ケア」で叶える
“頭から整う”深いリセット
最近、「頭が重い」「考えすぎて疲れる」「眠りが浅い」――
そんな声を多く耳にします。
現代人の多くが抱えるこの“頭の疲れ”こそ、**脳疲労(のうひろう)**と呼ばれる状態です。
そして、頭のこりや重だるさを癒すケアとして人気なのが「ヘッドマッサージ」。
しかし、青葉台「ちゅ楽」では、単なるリラクゼーションに留まらない、
**“脳から整えるケア”=『脳疲労ケア』**を提供しています。
■ 「脳疲労」とは? 頭がこる理由
デスクワーク・スマホ・ストレス・浅い呼吸…。
これらが続くと、脳や神経が常に「ON」の状態になり、
自律神経が乱れやすくなります。
その結果、次のような不調が現れます:
-
頭が重い、締め付けられるような感覚
-
目の奥の痛みやかすみ
-
寝つきが悪く、眠っても疲れが抜けない
-
首・肩こりが慢性化
-
集中力や思考力の低下
この状態こそ、脳の“過活動”による疲労。
つまり、体の疲れではなく「神経の疲れ」なのです。
■ 「ヘッドマッサージ」との違い ― 深部から神経に届くケア
一般的なヘッドマッサージは、頭皮をもみほぐし血行を促進します。
それに対し、ちゅ楽の《脳疲労ケア》は、
神経・筋膜・自律神経のバランスを整えることを目的にしています。
頭・首・顔・耳周りなど、神経が集中するポイントをゆっくり丁寧に解放していくことで、
交感神経(緊張)と副交感神経(リラックス)の切り替えを促します。
施術中は、ふっと呼吸が深くなり、
「頭の中が静かになる」「久しぶりに“空っぽ”になれた」と感じる方も多くいらっしゃいます。
■ 眠れない夜、浅い眠りにも効果的
脳疲労が進むと、睡眠の質が低下します。
ちゅ楽の《脳疲労ケア》では、頭部をやさしく緩めることで、
脳波が「休息モード」に切り替わり、深い眠りを誘発します。
実際、施術中に眠ってしまう方も多く、
「久しぶりにぐっすり眠れた」「翌朝の目覚めが全然違う」との声も。
睡眠薬に頼らず、自然に眠れる体を取り戻す――
それが、ちゅ楽のヘッドケアが目指す“本当のリラックス”です。
■ 眼精疲労・顔のむくみにもアプローチ
脳疲労ケアでは、目の周囲・こめかみ・頭頂部などを丁寧に解放していくため、
眼精疲労や顔のむくみ、くすみにも効果的です。
「目が開きやすくなった」「顔色が明るくなった」など、
美容面での変化を感じる方も少なくありません。
■ 頭から整える、全身のリセット
頭部は全身の司令塔。
脳や神経が整うと、自然と呼吸が深くなり、
筋肉のこわばりや血流も改善されていきます。
つまり、頭をゆるめることは、
全身の疲れ・痛み・冷え・自律神経の乱れを整える近道なのです。
■ 青葉台で「ヘッドマッサージ」を探している方へ
もし今、
-
頭が重くてスッキリしない
-
寝ても疲れが抜けない
-
目の奥がつらい
-
常に考えすぎてしまう
そんな状態が続いているなら、
ぜひ《脳疲労ケア》を体験してみてください。
「ただのヘッドマッサージ」とは違う、**“脳が休まる感覚”**を味わえるはずです。
あなたの思考と体を静かにリセットし、
明日を軽やかに迎えるための時間を――
青葉台「ちゅ楽」でお過ごしください。
(ちゅ楽)
2025年11月18日 07:58





"もみほぐし"のその先へ ― 青葉台ちゅ楽のボディケアで感じる、本当の軽さ

「最近、疲れが取れない」「肩や腰の重だるさが抜けない」――そんな時、多くの方が探すのが「もみほぐし」。
しかし、ただ筋肉を揉むだけでは、その場限りのスッキリ感で終わってしまうことも少なくありません。
青葉台「ちゅ楽」の《ボディケア》は、“もみほぐし”の心地よさを超えた、「本当に軽くなる」ケアを目指しています。
■ ちゅ楽のボディケアとは
ちゅ楽のボディケアは、筋肉や関節の動きに着目した施術です。
深層の筋肉(インナーマッスル)にまでアプローチしながら、筋膜や関節まわりの張りを丁寧に緩めていきます。
目的は「痛みを取ること」ではなく、「自然な動きを取り戻すこと」。
慢性的なコリや疲れは、筋肉だけでなく“関節の動き”の悪さから生じていることも多いのです。
そのため、ちゅ楽のボディケアでは、押す・伸ばす・回すといった多彩な手技を組み合わせ、体を立体的にほぐしていきます。
■ 「もみほぐし」と「リリース整体」の違い
ちゅ楽には、院長が行う特別メニュー「リリース整体」もありますが、ボディケアはそれとは異なるアプローチです。
リリース整体が“根本改善”を目的とした専門的な施術であるのに対し、
ボディケアは“リラックスしながら体を軽くしたい方”におすすめのメニュー。
「強すぎないけど、ちゃんと効く」――そんな絶妙な圧で、全身の筋肉を解きほぐしていきます。
もみほぐしのようなリズム感と手の温もりで、自然と体も心もほぐれていくのが特長です。
■ 3つのコースで、あなたに合った癒しを
ちゅ楽では、ボディケアを3つのコースからお選びいただけます。
-
ボディケア30分:部分集中ケア。首肩・腰・脚など、気になる箇所を集中的にほぐします。
-
ボディケア60分:全身をバランスよく整えたい方におすすめ。日常的な疲労回復にも。
-
ボディケア90分:深いコリや慢性疲労を感じる方に。全身をじっくり解きほぐし、巡りを整えます。
その日の体調や目的に合わせて選べるのも、リピートされる理由のひとつです。
■ 「もみほぐし」では届かない深いリラックスを
疲れやコリが抜けない原因のひとつに、“無意識の緊張”があります。
仕事やストレスによって交感神経が優位になると、筋肉は常に軽く緊張し、力が抜けにくい状態になります。
ちゅ楽のボディケアでは、呼吸に合わせたリズムで施術を行い、自然と副交感神経を優位に導きます。
そのため、施術中に眠ってしまう方も多く、「もみほぐし以上の深いリラックス」を感じていただけます。
■ コリを“感じにくい体”へ
一時的にほぐれても、すぐにまたコリが戻ってしまう――。
そんな方にこそ、ちゅ楽のボディケアを受けてほしい理由があります。
それは、筋肉をほぐすだけでなく「関節の動き」「体の使い方」を整えているから。
体の軸が自然な位置に戻ることで、筋肉への負担が軽減され、コリにくい状態が続きやすくなります。
また、血流やリンパの巡りも良くなるため、施術後の軽さが長く続くのも特徴です。
■ こんな方におすすめ
-
デスクワークや立ち仕事で肩・腰・背中がつらい
-
普段から力が抜けにくく、リラックスが苦手
-
睡眠の質を上げたい
-
マッサージを受けてもすぐ戻る
-
強すぎる施術は苦手だけど、しっかりほぐしてほしい
そんな方にとって、ちゅ楽のボディケアは“もみほぐし以上の満足感”を感じていただけるはずです。
■ 青葉台で「もみほぐし」をお探しの方へ
青葉台エリアにも多くの「もみほぐし店」がありますが、
ちゅ楽のボディケアは「癒し」と「整え」を両立させた特別な施術です。
手の温もりと確かな技術で、あなたの体の奥にある“本当の疲れ”を解きほぐします。
ちゅ楽のボディケアで、頑張る体を一度リセットしてみませんか?
筋肉も心もやわらかくほどけていくような、深い安らぎをぜひ体感してください。
ご予約・お問い合わせはお気軽に。
あなたの体が軽くなる瞬間を、ちゅ楽が丁寧にサポートいたします。
(ちゅ楽)
2025年11月17日 07:43





「流すだけじゃないリンパケア」― 体の"巡り"を整える、ちゅ楽式アプローチ

「リンパを流すとスッキリする」「リンパマッサージでデトックス」
そんな言葉を耳にする機会が増えました。
けれど実は、リンパの流れを良くする=強く流すことではない、ということをご存じでしょうか?
本来のリンパケアとは、“流れを作る土台を整えること”。
青葉台『ちゅ楽』では、アロマトリートメントやインディバを通して、
この“巡りの本質”にアプローチしています。
■ リンパとは「体の排水システム」
リンパは、体の中をゆっくり流れる“第二の循環”です。
血液が酸素や栄養を運ぶのに対し、リンパは老廃物や余分な水分を回収して排出する役割を担っています。
しかしこの流れは、血液と違ってポンプ(心臓)がありません。
筋肉の動きや呼吸、姿勢のバランスによって左右されるため、
デスクワークや冷え、ストレスなどで簡単に滞ってしまうのです。
「脚がむくむ」「顔が重い」「体がだるい」――
これらは、リンパが滞っているサインかもしれません。
■ 強く流すマッサージでは、
かえって流れが悪くなることも
「リンパマッサージ」と聞くと、“強く押して流す”イメージを持つ方も多いでしょう。
ですが実際には、リンパ管はとても繊細で、強い圧をかけると潰れてしまうこともあります。
一時的にスッキリしたように感じても、すぐに戻ってしまう…
そんな経験がある方は、「流す」だけのケアになっている可能性があります。
大切なのは、流す前に整えること。
筋肉・神経・血流・呼吸が整うことで、自然とリンパは“自分で流れる”ようになります。
■ ちゅ楽のアロマトリートメントが
“流れを整える”理由
『ちゅ楽』のアロマトリートメントは、
いわゆる“リンパマッサージ”のような流す施術ではなく、
香り・呼吸・タッチを通して神経と循環を整えるケアです。
植物のエッセンシャルオイルは、香りが脳へ届くと自律神経に働きかけ、
血流・リンパ・ホルモンのリズムを整えます。
また、手の温もりによるゆるやかな刺激が筋肉を緩め、
自然と体内の流れが再起動。
「むくみが取れただけでなく、心まで軽くなった」と感じる方が多いのは、
まさに神経レベルでの巡りが整った証拠です。
■ インディバで「深部のリンパ」まで活性化
さらに、体の奥の循環を改善したい方にはインディバとの組み合わせがおすすめ。
高周波エネルギーによって体内に熱を生み出すインディバは、
深部の血管やリンパ管を拡張し、老廃物の排出をスムーズにします。
特に、
-
慢性的なむくみ・冷え
-
肩や腰の張り
-
生理前の不調やだるさ
などは、インディバの「深部温熱 × アロマのリラックス」で変化を感じやすい症状です。
体が温まり、リンパが流れやすくなることで、
「体が軽い」「肌ツヤがよくなった」「眠りが深くなった」などの声も多くいただきます。
■ リンパを整えるとは、
“生きるリズム”を整えること
リンパが滞る=体内の循環が止まる、ということ。
これは、肉体的な疲れだけでなく、心の停滞にもつながります。
現代人の多くが、
・座りっぱなし
・ストレス過多
・睡眠不足
といった“巡りを止める生活”をしています。
だからこそ、意識的に「整える時間」を持つことが大切です。
『ちゅ楽』のアロマやリリース整体は、その“リズムの再起動スイッチ”になります。
■ ちゅ楽式リンパアプローチの流れ
-
カウンセリング:体の冷え・むくみ・疲労・ストレスの状態を確認
-
施術設計:アロマの香りを選び、筋膜や神経のバランスをチェック
-
施術:呼吸に合わせたタッチで筋肉・神経・循環を同時に整える
-
アフター:体の巡りが整った“軽さ”と“温かさ”を実感
リンパを“流す”のではなく、
体が自分で流せる状態をつくる――これがちゅ楽の考えるリンパケアです。
■ こんな方におすすめ
-
むくみや冷えが気になる
-
肩や腰の疲れが抜けない
-
寝ても疲れが取れない
-
頭が重く、集中力が落ちている
-
ストレスで呼吸が浅くなっている
リンパの滞りを放置すると、体調不良だけでなく、免疫やホルモンバランスにも影響します。
だからこそ、“流す”より“整える”ケアが必要なのです。
■ まとめ ― 体の流れが変わると、心も軽くなる
リンパは「体の声」を映す鏡です。
体を整えることは、心を整えることにもつながります。
『ちゅ楽』のアロマトリートメントとインディバで、
体の内側から“巡り”を取り戻してみませんか?
「なんとなく疲れている」「冷えやむくみを感じる」
そんなときこそ、自分の中の“流れ”に耳を傾けてあげる時間を。
その小さなきっかけが、体調も気分も大きく変えていきます。
(ちゅ楽)
2025年11月16日 07:26





揉んでも治らない"肩こり"の真実 ― あなたの体が教えている「意外なサイン」とは?

肩こり。
多くの人が悩むこの症状、実は「肩」そのものだけが原因ではないことをご存じですか?
マッサージやストレッチをしてもすぐ戻る――そんな方こそ、体の**“別の場所”**に目を向けてみる必要があります。
今回は、青葉台のリラクゼーションサロン『ちゅ楽』が、
「意外な肩こりの原因」とその改善アプローチをお伝えします。
ただの「もみほぐし」では届かない、根本ケアの世界へようこそ。
1. 肩こりの本当の原因は“肩”じゃない?
「肩がこっている=肩の筋肉が固まっている」と思いがちですが、実際はもっと複雑です。
慢性的な肩こりの多くは、神経・筋膜・自律神経・内臓の疲れが絡み合って起こります。
例えば――
-
呼吸が浅い人:酸素不足で首肩の筋肉が常に緊張
-
ストレスが多い人:交感神経が優位になり、肩甲骨まわりの筋肉が硬直
-
胃腸が弱っている人:横隔膜の動きが制限され、肩・首が引っ張られる
-
眼精疲労が強い人:視神経と連動して後頭部~首が凝る
つまり、肩を揉むだけでは解決しないのです。
むしろ、根本的には「体の使い方」「呼吸の浅さ」「神経の緊張」を整える必要があります。
2. なぜ“揉むだけ”では戻ってしまうのか?
肩こりの人の筋肉は、一見ガチガチに固まっていますが、その奥にあるのは防御反応。
「これ以上動かすと危険だ」と脳が判断し、筋肉をロックしてしまっているのです。
だから、強く揉むと一時的には軽く感じても、
脳が「危険」と認識して再び緊張を戻してしまう。
この“戻り”が、慢性化の一因です。
『ちゅ楽』では、こうした反応をリセットするために、
神経・筋膜・呼吸の3つに着目しています。
3. 神経と筋膜をゆるめる「リリース整体」
リリース整体では、筋肉だけでなく、筋膜や神経の通り道にアプローチ。
優しい圧とリズムで神経反射を落ち着かせ、脳に「安全だよ」と伝えます。
これにより、自然と筋肉が“自ら緩む”状態を作り出します。
実際、肩こりがひどい方ほど、「肩以外」を施術したときに軽くなるケースが多いです。
たとえば、
-
胸の筋膜を緩めると、呼吸が深くなり肩が下がる
-
骨盤を整えると、首の力みが抜ける
-
足裏を刺激すると、背中のハリが緩む
体は“つながっている”という事実を、施術を通して実感される方がほとんどです。
4. 自律神経の乱れも肩こりをつくる
ストレスや睡眠不足が続くと、交感神経が過剰に働きます。
この状態では、体は常に“戦闘モード”になり、肩や首がガチガチに。
ここで有効なのが、『ちゅ楽』のアロマトリートメントや脳疲労ケアです。
香りやタッチによって副交感神経を優位に導くことで、
自律神経のバランスを整え、筋肉の緊張も自然に緩みます。
「肩を触っていないのに肩が軽くなった」という感想が多いのも、その証拠です。
5. “温める力”で回復を早める
― インディバの相乗効果
肩こりの改善には血流の回復も欠かせません。
当店で人気のインディバは、深部から温めて代謝を高め、
硬くなった筋膜や神経の通りをスムーズにします。
整体で筋膜をリリースした後にインディバを行うことで、
「肩が動かしやすくなった」「夜ぐっすり眠れた」という方が多数。
これは単なる温熱効果ではなく、細胞レベルの活性が起こっているからです。
6. 肩こり改善の鍵は「感覚を取り戻す」こと
多くの人が自分の肩の状態に“鈍感”になっています。
「こってるのが普通」「もう慣れた」と感じてしまうと、
本来の柔らかさや軽さを忘れてしまうのです。
リリース整体やアロマトリートメントを受けた方がよく言うのが、
「こんなに呼吸しやすかったんだ」「体ってここまで軽いんだ」という驚き。
それは、感覚が戻った瞬間です。
肩こりを治すとは、単に筋肉を緩めることではなく、
“自分の体を感じる力”を取り戻すことでもあります。
7. 今月限定:半額キャンペーン
現在、『ちゅ楽』では11月限定で、
インディバとセットのメニューが半額キャンペーン中です。
リリース整体・アロマトリートメント・ヘッドケア・ボディケアのいずれかに
インディバ(30・60・90分)を組み合わせて受けていただくと、
セットのもう一方が半額になります。
「肩を揉んでも治らない」方にこそ、
この多角的なケアをぜひ体験していただきたい。
体が“本来の軽さ”を思い出す感覚を、あなたも感じてみませんか?
まとめ
肩こりの本当の原因は、筋肉の硬さではなく“体全体のバランス”です。
神経・呼吸・自律神経・血流――それらを整えることが、根本改善の鍵。
青葉台『ちゅ楽』では、
そのすべてにアプローチするオーダーメイドのケアを行っています。
肩こりを「揉んで治す」から「整えて変える」へ。
今こそ、体の声に耳を傾けてみませんか?
(ちゅ楽)
2025年11月15日 07:13





オイルマッサージを探している方へ

――香りと手技で“芯から解ける”アロマトリートメントの魅力
オイルマッサージと聞くと、多くの方が「リラックスできそう」「癒されそう」とイメージするでしょう。
確かに、オイルマッサージは身体の疲れだけでなく、心の緊張まで解きほぐしてくれる特別なケアです。
青葉台にもオイルマッサージを受けられるお店が増えていますが、**「どこで受けても同じ」**ではありません。
『ちゅ楽』のアロマトリートメントは、ただのリラクゼーションではなく、身体と心の“本当の回復”を目的とした施術です。
その理由を少し、掘り下げてご紹介します。
■ オイルマッサージの魅力は「香り」と「流れ」
アロマオイルの香りには、自律神経を整えたり、心の緊張をほぐしたりする作用があります。
たとえばクロモジは安眠を促し、柑橘系は気持ちを明るく、ニオイコブシはホルモンバランスを整えるなど、
香りにはそれぞれに“心と体を動かす力”があります。
『ちゅ楽』では、その日の体調や気分を伺いながら、お一人おひとりに合わせたブレンドを行います。
香りの力と熟練の手技が合わさることで、呼吸が深くなり、筋肉だけでなく神経の緊張までゆるんでいく──
そんな感覚を体験していただけます。
■ 深層のこりや自律神経にも届く手技
ちゅ楽のアロマトリートメントは、ただ表面をなでるだけではありません。
整体・筋膜リリースの知識を持つセラピストが、筋肉の深部やリンパの流れ、自律神経の反応まで見極めながら施術します。
肩こりや背中のはり、むくみ、冷えといった悩みも、体の「流れ」を整えることで改善へ導きます。
また、交感神経が優位になりがちな現代人にとって、アロマの香りとゆったりした圧は副交感神経を刺激し、
「眠ってしまうほどのリラックス状態」をつくり出します。
■ 心のリセットにもなる時間
疲れているのに眠れない。
何もしていないのに気持ちが焦る。
そんなとき、体だけでなく**心の“緊張スイッチ”**も入りっぱなしになっています。
アロマトリートメントは、そのスイッチをやさしくオフにする時間。
香りとタッチで脳のストレス反応を鎮め、心身をリセットしていきます。
施術後は「目の奥がすっきりした」「頭が軽くなった」「呼吸が深くなった」と感じる方が多く、
リピーターの方からは「寝つきが良くなった」「肩の重さが消えた」とのお声もいただきます。
■ 青葉台で“本当の癒し”を求めるなら
『ちゅ楽』のアロマトリートメントは、
・疲れが抜けにくい方
・自律神経の乱れを感じる方
・眠りの質を上げたい方
・肩こり・冷え・むくみが気になる方
・ストレスで心が張りつめている方
におすすめです。
オイルマッサージの気持ちよさと、整体的アプローチの深さを兼ね備えた“ちゅ楽ならではの癒し”。
静かな個室で香りに包まれながら、日常のストレスをリセットしてみませんか?
■ 終わりに
オイルマッサージを探している方が、本当に求めているのは「癒し」ではなく「解放」かもしれません。
体の疲れだけでなく、心のこわばりまでやさしくほぐす――それが『ちゅ楽』のアロマトリートメントです。
香りに導かれ、心身がふわっと軽くなる。
そんな“自分を取り戻す時間”を、ぜひ体験してください。
(ちゅ楽)
2025年11月14日 07:10





肩こりの奥にある"冷えと緊張"をゆるめる

11月限定「インディバ×他メニュー半額キャンペーン」で、冬のこりを根本から解放
朝晩の冷え込みが厳しくなり、気づけば肩がギュッとすくんでいませんか?
「最近、肩がパンパンに張っている」「マッサージしてもすぐに戻る」「頭痛や目の疲れも増えてきた」──
そんな声が増える季節です。
実は、冬に肩こりが悪化するのは“冷え”と“自律神経の乱れ”が関係しています。
寒さで血流が滞り、筋肉が硬直。さらに、寒暖差やストレスで交感神経が優位になることで、
肩や首まわりが常に緊張してしまうのです。
そんな冬特有の「冷え性肩こり」におすすめなのが、
青葉台「ちゅ楽」の11月限定・インディバ×他メニュー半額キャンペーンです。
インディバの“深部温熱効果”で体の奥から温め、筋肉の緊張と血流の滞りを根本から改善。
さらに、他メニューとの組み合わせで、あなたの肩こりの原因を多角的にアプローチします。
■ 肩こりの根本原因は「深部の冷え」と「筋膜のこわばり」
肩こりの多くは、表面の筋肉だけでなく、その奥にある筋膜や神経の通り道が硬くなっていることが原因です。
表面をもみほぐしても一時的な軽さしか得られないのは、根本の“冷え”が解消されていないからです。
インディバは、体内で「ジュール熱(摩擦熱)」を発生させることで、
筋肉・筋膜・血管の奥まで熱を届けることができる特殊な温熱機器。
これにより、冷えて固まった深層筋がじんわりとゆるみ、血液やリンパの流れが活性化します。
結果として、
-
肩・首・背中の張りや痛みが軽減
-
頭痛や眼精疲労の緩和
-
巻き肩や猫背の改善
といった変化が感じられます。
■ 温めるだけじゃない!ちゅ楽の「組み合わせ施術」
ちゅ楽の強みは、インディバを単体で終わらせないこと。
体の状態に合わせて、他メニューとの組み合わせで最大限の効果を引き出します。
-
リリース整体 × インディバ
→ 深部の筋膜リリースで神経や血管の通り道を整え、肩こりの再発を防止。 -
アロマトリートメント × インディバ
→ 自律神経を整え、ストレス由来の肩こりを根本から緩和。 -
ヘッドケア × インディバ
→ 脳疲労をリセットし、頭重感や眼精疲労の改善に効果的。
施術後は「肩だけでなく体全体が軽くなった」「呼吸がしやすくなった」
といった感想を多くいただいています。
■ 11月限定キャンペーン内容
今月限定で、インディバ(30・60・90分)のいずれかを受けていただくと、
他のメニュー(ボディケア・アロマ・ヘッドケア・リリース整体)が半額になります!
たとえば:
-
インディバ60分+ボディケア60分 → ¥14,850(通常¥18,700)
-
インディバ60分+アロマ30分 → ¥13,750(通常¥16,500)
-
インディバ60分+ヘッドケア20分 → ¥12,265(通常¥13,530)
体を温めながら筋肉をゆるめ、疲労をためない冬の体を整える絶好のチャンスです。
■ 肩こりを放置すると…
肩こりは「体からのサイン」です。放っておくと、
-
頭痛・めまい
-
不眠・集中力低下
-
自律神経の乱れ
-
肩甲骨や背中の張りから腰痛へ波及
といった慢性的な不調へと発展します。
インディバで血流を回復させ、リリース整体やアロマで整えることで、“治る体質”へ導くことができます。
■ 今、肩こりを「温めながら整える」
11月の冷えが本格化する今こそ、体の奥から整えるチャンスです。
「温め×整える」というダブルアプローチで、肩こりを根本から改善しましょう。
疲れをためこまず、軽やかな冬を過ごすために──
ぜひこの機会に、青葉台「ちゅ楽」のインディバ×他メニュー半額キャンペーンをご体験ください。
体がゆるむと、心も軽くなります。
あなたの「もう戻らない肩こり」に、根本からアプローチします。
(ちゅ楽)
2025年11月13日 07:50





ピラティスを始める前に ― "動ける体"を整える土台づくり

青葉台で増えるピラティスブームと、ちゅ楽が提案する新しいアプローチ
近年、青葉台エリアでもピラティススタジオが増え、「姿勢を整えたい」「体幹を鍛えたい」と始める方が急増しています。
ピラティスは、呼吸とともに深層筋(インナーマッスル)を鍛え、
体の中心からバランスを整えるメソッドとして、40〜60代の女性を中心に注目されています。
しかし、実際に通い始めた方の中には──
「ピラティスをすると腰が張る」「動きが硬くてインストラクターに言われた通りにできない」「気持ちはいいけど、なかなか変化が感じられない」
そんな声も少なくありません。
実は、ピラティスで成果を出すためには、“動ける体の準備”が必要なのです。
■ ピラティスの効果を左右する「身体の柔軟性」と「感覚」
ピラティスの基本は、筋力トレーニングというより「自分の体を感じながら動かすこと」。
そのため、筋膜の癒着や関節の歪み、神経の緊張が強い状態では、体幹をうまく使えず、正しいフォームが取れません。
例えば──
・猫背や反り腰があると、腹筋を使う動作が苦しくなる
・肩甲骨が硬いと、腕の動きが制限され呼吸が浅くなる
・骨盤が前傾していると、ピラティスで腰を痛めるリスクが上がる
こうした「体の制限」を解放することが、ピラティス効果を最大化する第一歩です。
■ そこで大切なのが、“動ける体をつくるケア”
青葉台「ちゅ楽」では、ピラティスやヨガ、トレーニングを行う方々の「ベースケア」として、
リリース整体・アロマケア・インディバを組み合わせた施術を行っています。
特に人気の「リリース整体」は、筋膜・関節・神経への総合的なアプローチで、
・動かしにくい部位の可動域を広げる
・体幹が働きやすい状態をつくる
・姿勢を自然に整える
といった“機能改善”を目的とした手技です。
また、アロマケアでは呼吸を深め、自律神経のバランスを整えることで、
ピラティスの「呼吸と連動した動き」をスムーズに導きます。
体をゆるめながら、神経系から動きを再教育していく──それがちゅ楽の強みです。
■ 「ケア × 動き」で、相乗効果が生まれる
ピラティスで体を動かすことは、筋肉の再教育。
ちゅ楽のケアは、その“前準備”として、動かせる体の環境を整えます。
この2つを組み合わせることで、次のような相乗効果が期待できます。
-
呼吸が深くなり、体幹の使い方が自然に身につく
-
肩こり・腰痛を予防しながら、姿勢をキープしやすくなる
-
トレーニング中の“感覚”が明確になり、フォームが安定する
-
疲労がたまりにくく、継続できる体へ変わる
「体を鍛える前に、まず整える」──この順番を意識するだけで、体の変化はまるで違ってきます。
■ ピラティスを始めた方・始めたい方におすすめのケアプラン
ちゅ楽では、ピラティスを行う方に合わせた施術をご用意しています。
-
リリース整体 :体の歪み・可動域を整えて、正しく動ける体へ
-
アロマトリートメント :呼吸と自律神経を整え、深いリラックスを
-
インディバ:深部温熱で代謝・筋肉・神経をサポート
初回カウンセリングでは、現在の体の状態や、「ピラティスを始めたい」と思っていることを丁寧にお伺いし、
最適な組み合わせをご提案します。
■ 「動ける体づくり」から始めるピラティスライフ
ピラティスは、体を「鍛える」だけでなく、「整える」ためのメソッドです。
しかし、硬さや歪みを抱えたまま動かしても、効果が半減してしまいます。
ちゅ楽では、その“土台づくり”を担う存在として、ピラティスを始める方・続けている方の体をサポートしています。
もし今、
「ピラティスをしても思うように体が動かない」
「呼吸が浅くて体幹がうまく入らない」
「肩や腰に負担が出てしまう」
そんな悩みがある方は、ぜひ一度、ちゅ楽のケアを体験してみてください。
筋肉や関節がしなやかに動くようになると、ピラティスの効果が何倍にも高まります。
そして、日常の姿勢や呼吸、立ち姿そのものが美しく変わっていくはずです。
青葉台のピラティスブームの中で、**“動ける体を整える場所”**として、
ちゅ楽はあなたのコンディショニングパートナーになります。
まずはお気軽にご相談ください。あなたの体が“整って動く”瞬間を、一緒に実感しましょう。
(ちゅ楽)
2025年11月12日 12:02





【11月限定】インディバ×他メニュー半額キャンペーン

冷えと疲れが深まる季節に、“温め×整える”贅沢ケアを
秋が深まり、朝晩の冷え込みが一段と増してきました。
「体が冷えてなかなか温まらない」「疲れが抜けにくい」「肩や腰が固まっている」──そんな声が多く聞かれる季節です。
この時期、体調を左右するカギとなるのが、“深部の温め”と“巡りの回復”。
そこで青葉台「ちゅ楽」では、11月限定でインディバと他メニューを組み合わせた特別キャンペーンを実施しています。
インディバ(30分・60分・90分のいずれか)と一緒に、
ボディケア・アロマ・ヘッドケア・リリース整体のいずれかを組み合わせると、そのメニューが半額に!
つまり、今だけ“2つの相乗効果”を体験できる贅沢な1ヶ月です。
◆ インディバとは?
「温める」だけじゃない、細胞レベルのケア
インディバは高周波温熱機器で、体の深部を“自ら発熱する”状態に導く技術です。
一般的な温熱法とは違い、体内の細胞が活性化し、自律神経やホルモンのバランスを整える働きがあります。
冷えに悩む女性や、慢性的な疲労・むくみ・筋肉のコリを抱える方に特におすすめ。
内臓から温まり、代謝が上がることで、施術後の“軽さ”や“ポカポカ感”が長時間続きます。
しかし、実はインディバの真価は「他の手技と組み合わせたとき」にこそ発揮されるのです。
◆ インディバ×アロマ ―
自律神経を深く整える極上の癒し
アロマトリートメントの特徴は、香りと手の温もりによって副交感神経を優位にすること。
インディバで深部を温めてからアロマを受けると、血流とリンパの流れが高まり、精油成分の吸収率もぐっと上がります。
冷え性・不眠・PMS・ストレス過多の方には、この組み合わせが最適。
「ただ気持ちいいだけでなく、心が静まり、体が“ととのう”感覚がある」──
多くのお客様がそう感じられる、まさに“整う時間”です。
◆ インディバ×リリース整体 ―
深層筋と神経の働きを解放する
リリース整体は、固まった筋膜や深層筋のねじれを整え、体の可動域を広げていく手技です。
そこにインディバを組み合わせると、筋肉の緊張が早くゆるみ、関節の動きもスムーズになります。
特に、慢性的な肩こり・腰痛・膝痛など、“どこに行っても改善しなかった痛み”を抱える方におすすめ。
温熱で筋肉を柔らかくしながら、神経・筋膜・骨格を一体的に整えることで、
「その場で体が軽くなる」「動きやすくなる」変化を実感できます。
◆ インディバ×ヘッドケア ―
脳疲労のリセットに最適
最近注目されている“脳疲労”は、冷えや自律神経の乱れとも密接な関係があります。
頭部や首周りが冷えると、血流が滞り、集中力低下や不眠を引き起こすことも。
インディバで首~肩・頭部を温めたあとにヘッドケアを行うと、
頭皮の血流が活発になり、脳の過緊張がスーッと解放されるのを感じられます。
目の疲れ・ストレス・睡眠の質を改善したい方には、まさにこの時期ぴったりの組み合わせです。
◆ インディバ×ボディケア ―
疲れを“抜く”ための最短ルート
「疲れが取れない」「寝てもだるい」──それは、筋肉が硬くなって血流が滞っているサイン。
インディバで深部の温度を上げたあとにボディケアを行うと、
硬い筋肉がゆるみ、手技の効果が何倍にも高まります。
特にデスクワークで背中や脚が重だるい方には、
“温めてほぐす”このセットが最強のリカバリーメニュー。
まるで「体の中からリセットされるような軽さ」を実感できます。
◆ 11月限定キャンペーン詳細
-
対象期間:2025年11月1日〜11月30日
-
対象メニュー:
インディバ30分・60分・90分のいずれか +
ボディケア・アロマ・ヘッドケア・リリース整体のいずれか -
特典内容:
インディバと組み合わせた他メニューが半額!
※どの組み合わせでもOKです。たとえば…
・インディバ60分 × アロマ60分 → アロマが半額
・インディバ30分 × リリース整体60分 → 整体が半額
冷え・疲労・ストレスが溜まりやすいこの季節に、
「温め×整える」のダブルアプローチで、体を根本からリセットしませんか?
◆ 体の声を聞きながら、冬に備える11月に
11月は、体が“冬モード”に切り替わる大切な時期です。
冷えやすくなった体を放置してしまうと、年末にかけて疲れが一気に出てしまうことも。
インディバの温熱と手技の相乗効果で、今から巡りと代謝を整えておくことで、
冬を元気に乗り切る“温まる体”を作ることができます。
青葉台「ちゅ楽」で、この秋だけの特別ケアをぜひ体験してください。
あなたの体が本来持つ“回復力”が、きっともう一度、動き出します。
(ちゅ楽)
2025年11月11日 12:30





<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。