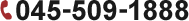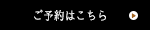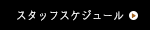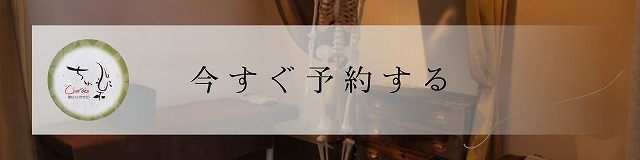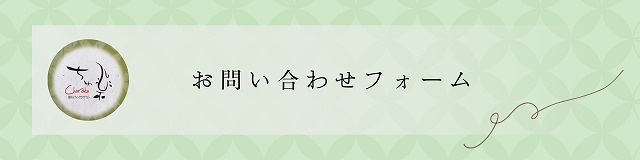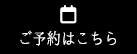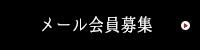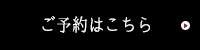カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2026年1月 (5)
- 2025年12月 (26)
- 2025年11月 (29)
- 2025年10月 (31)
- 2025年9月 (30)
- 2025年8月 (25)
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (3)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (3)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (6)
- 2024年3月 (7)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (5)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (3)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (5)
- 2023年5月 (8)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (10)
- 2023年2月 (10)
- 2023年1月 (27)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (2)
- 2022年7月 (3)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (5)
- 2021年4月 (4)
- 2021年3月 (10)
- 2021年2月 (7)
- 2021年1月 (5)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (6)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (9)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (3)
- 2020年5月 (4)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (3)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (7)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (5)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (5)
- 2019年7月 (8)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (9)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (4)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (8)
- 2018年9月 (3)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (7)
- 2018年3月 (6)
- 2018年2月 (9)
- 2018年1月 (8)
- 2017年12月 (12)
- 2017年11月 (9)
- 2017年10月 (13)
- 2017年9月 (15)
- 2017年8月 (19)
- 2017年7月 (12)
- 2017年6月 (16)
- 2017年5月 (8)
- 2017年4月 (20)
- 2017年3月 (14)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (11)
- 2016年12月 (6)
- 2016年11月 (7)
- 2016年10月 (9)
- 2016年9月 (5)
- 2016年8月 (4)
- 2016年7月 (8)
- 2016年6月 (6)
- 2016年5月 (16)
- 2016年4月 (9)
- 2016年3月 (10)
- 2016年2月 (10)
- 2016年1月 (8)
- 2015年12月 (7)
- 2015年11月 (10)
- 2015年10月 (13)
- 2015年9月 (8)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (15)
- 2015年6月 (17)
- 2015年5月 (16)
- 2015年4月 (20)
- 2015年3月 (18)
- 2015年2月 (14)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (3)
- 2014年11月 (9)
- 2014年10月 (9)
- 2014年9月 (8)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (13)
- 2014年5月 (11)
- 2014年4月 (12)
- 2014年3月 (5)
- 2014年2月 (7)
- 2014年1月 (10)
- 2013年12月 (6)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (6)
- 2013年9月 (7)
- 2013年8月 (5)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (8)
- 2013年5月 (5)
- 2013年4月 (6)
- 2013年3月 (4)
最近のエントリー
HOME > スタッフブログ > アーカイブ > 体について > 11ページ目
スタッフブログ 体について 11ページ目
四十肩・五十肩で腕が上がらない...放置せず改善するための具体的な方法

四十肩・五十肩とは?「年齢のせい」だけではない真実
「肩が痛くて腕が上がらない…」そんな悩みを感じる40代〜60代の方に多いのが、いわゆる“四十肩・五十肩”。
実際の医学的な名称は「肩関節周囲炎」と呼ばれ、肩の関節や周囲の筋肉・靭帯・関節包に炎症が起こる状態です。
発症のきっかけは人によって異なり、はっきりと原因が分からない場合も多いですが、年齢による組織の変化だけでなく、
日常の姿勢や使い方、血流不良、ストレスなど複数の要因が関係していると考えられています。
四十肩・五十肩の典型的な症状
四十肩・五十肩の特徴は「ある日突然、肩に強い痛みが出る」こと。
特に夜間痛が強く、眠れないほどの痛みで生活に支障をきたす方も少なくありません。
初期は動かすだけで鋭い痛みを感じ、腕を上げる・後ろに回すといった動作が難しくなります。
その後、徐々に痛みは落ち着くものの、可動域が制限され「肩が固まる(拘縮期)」状態に。
回復には数ヶ月から1年以上かかることもあり、「放っておけば自然に治る」と言われつつも、
長期化して日常生活に大きな影響を及ぼすのが実情です。
放置してしまうとどうなるのか?
「そのうち治るだろう」と放置してしまう方も多いですが、痛みや可動域制限が長引くと、
筋肉の萎縮や血流の悪化が進み、姿勢や動作にも悪影響を及ぼします。
服を着替える、髪を結ぶ、背中をかくといった日常の動作に不自由を感じるだけでなく、
肩をかばうことで腰や首に二次的な痛みを抱えてしまうケースもあります。
つまり、四十肩・五十肩は「肩だけの問題」ではなく、全身に広がるリスクを持つのです。
改善のために大切なこと
医学的に四十肩・五十肩は「自然に治る」とされますが、
実際は1〜2年も痛みや不自由を抱え続けるのは現実的ではありません。
そのために重要なのは「血流改善」「筋膜・関節の柔軟性回復」「痛みを抑えながらの運動療法」です。
特に初期の強い炎症期には無理に動かすのは逆効果となり、
炎症が落ち着いてきたタイミングで適切な施術やリハビリを行うことが効果的です。
リリース整体や温熱療法(インディバなど)で血流を促し、固まった筋膜や関節包を少しずつ緩めることで、
回復のスピードが格段に変わります。
ちゅ楽でのアプローチ
青葉台の「ちゅ楽」では、四十肩・五十肩の方に対してリリース整体・アロマ・インディバ 総合的なケアを行っています。
まずは痛みを和らげる温熱アプローチで血流を改善。そのうえで、肩だけにとらわれず
首・背中・胸郭といった周囲の動きを整えることで、肩にかかる負担を軽減します。
また、必要に応じてご自宅でできる簡単なセルフエクササイズもお伝えし、施術と日常ケアの両輪で回復をサポートします。
実際のお客様の声
「夜も眠れないほどの痛みが数回の施術で軽減した」
「服の脱ぎ着で痛みが走っていたのが、少しずつ楽になった」
「整形外科で『時間が経てば治る』と言われたけど、待つだけではつらかった」
実際に通ってくださるお客様の声からも、「放置せず早めにケアをする」大切さが伝わってきます。
あなたへのメッセージ
四十肩・五十肩は誰にでも起こりうる症状ですが、「もう歳だから仕方ない」と諦める必要はありません。
むしろ、早期に適切なケアを行うことで、痛みや不自由を最小限に抑え、生活の質を大きく改善できます。
もし今、肩の痛みで悩んでいるなら、「ちゅ楽」でその一歩を踏み出しませんか?
大切なのは「時間に任せて耐える」ことではなく、「あなたに合った改善の道」を見つけることです。
(ちゅ楽)
2025年9月 4日 23:14





膝の内側が痛いのはなぜ?考えられる原因とケア方法

膝の痛みを感じても「異常なし」と言われることがある
「歩くたびに膝の内側がズキッとする」
「正座や階段の上り下りがつらい」
40代〜60代の女性から、こうした膝の悩みをよく聞きます。
しかし病院では「異常なし」と言われたり、湿布を貼っても改善しなかったりすることが多いのも事実です。
「年齢のせいだから仕方ない」と思い込んでしまう方も少なくありません。
ですが、その裏には実は 加齢以外の原因 が隠れていることが多いのです。
膝の内側が痛むときに考えられる主な原因
膝の痛みにはいくつかの代表的な原因があり、それぞれ対策が異なります。
-
変形性膝関節症:膝の軟骨がすり減り、炎症によって内側に痛みが出る。
女性はホルモンの影響もあり、40代以降で発症しやすい。
-
半月板損傷:膝のクッションである半月板が傷つくことで痛みが出る。
若い人だけでなく中高年でも起こる。
-
鵞足炎(がそくえん):膝の内側にある腱の集まりが炎症を起こす。
階段や歩行で痛みやすい。
-
脳のエラー反応:膝に大きな異常がなくても、脳が「危険」と誤認して痛みを作り出す。
慢性痛の大きな要因で、「病院で異常なし」と言われたケースによく見られる。
膝の痛みと筋肉の関係
膝の痛みは膝だけの問題ではなく、筋肉の衰えや硬さが大きく関わります。
特に以下の筋肉が重要です。
-
太ももの内側(内転筋)
-
太ももの前(大腿四頭筋)
-
お尻の筋肉
40代以降は自然に筋肉量が減っていくため、同じ生活をしていても膝に負担がかかりやすくなります。
セルフケアの方法
膝の痛みを和らげるために、自分でできる工夫があります。
-
内転筋を鍛える:タオルやクッションを両膝に挟み、押し合う運動で膝を安定させる。
-
太ももの前をストレッチ:片足を後ろに曲げてお尻に近づけるように伸ばし、大腿四頭筋をゆるめる。
-
姿勢を整える:猫背や反り腰を直すことで膝への負担を減らす。
-
脳に安心を伝える:深呼吸や瞑想で副交感神経を働かせ、ヘッドケアやリリース整体で体をゆるめる。
脳が「大丈夫」と判断すると痛みが軽くなることがある。
サロンでの事例
50代女性のお客様は、病院で「異常なし」と言われても歩くたびに膝が痛み、趣味の旅行も楽しめないと悩まれていました。
施術では膝だけでなく太ももや腰回りを丁寧にほぐし、太ももの裏(ハムストリング)のトレーニングを取り入れて、膝の位置を調整。
数回のケア後には「階段がラクになった」「旅行に行けそう」と笑顔を取り戻されました。
このように、膝の痛みは単なる関節の問題ではなく、筋肉や健、脂肪と深く関わっていることを実感されたケースです。
まとめ
膝の内側の痛みは「加齢のせい」だけではありません。
変形性膝関節症や半月板損傷、鵞足炎といった体の異常に加え、筋力の低下や脳のエラー反応も関与します。
セルフケアで筋肉を整え、脳に安心を伝えることで、痛みがやわらぐ可能性があります。
もし「異常なし」と言われても痛みが続くなら、体と脳の両方にアプローチすることを考えてみてください。
そして一人で悩まず、専門家のサポートを受けることも大切です。
(ちゅ楽)
2025年9月 4日 09:34





【脳疲労とは?】集中力が続かない・やる気が出ないあなたへ
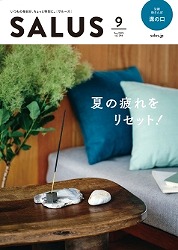
皆さん、「脳疲労」ってご存じですか?
先日、SALUSという東急の駅とかに置かれている雑誌に特集がありました。
もし、読んでない方はチェックしてみてくださいね。
「何をしても疲れが取れない」そんな経験はありませんか?
朝起きてもスッキリせず、仕事に集中できない。休みの日もぼんやりスマホを見ているだけで終わってしまう。
それは、体の疲れではなく “脳疲労” が原因かもしれません。
脳疲労とは?
医学的に「脳の情報処理が過剰になり、神経が休めない状態」を指します。
特に現代人はスマホ・パソコンを使う時間が長く、常に膨大な情報を浴びています。
脳には「前頭前野(考える部分)」と「大脳辺縁系(感情の部分)」があり、使いすぎるとバランスが崩れます。
結果、 集中力低下・気分の落ち込み・自律神経の乱れ が起こるのです。
脳疲労が引き起こす悪循環
-
集中できず、仕事のパフォーマンスが低下
-
眠っても疲れが取れない「睡眠の質の低下」
-
自律神経が乱れ、肩こりや頭痛、胃腸の不調が出る
-
気分が落ち込み、やる気が出ない
つまり、脳疲労は「心と体の両方の不調」をつくる根本原因なのです。
脳疲労と自律神経
-
交感神経(ON) と 副交感神経(OFF) の切り替えが乱れると、常に緊張状態が続く
-
脳疲労が蓄積すると コルチゾール(ストレスホルモン) が過剰分泌し、免疫力も低下する
「休んでいるのに休めない」という状態は、まさにこの仕組みによるものです。
脳疲労を回復する3つの方法
① 情報を遮断する“デジタルデトックス”
寝る前のスマホは控え、ブルーライトを浴びないだけで脳の休息が深まります。
② 呼吸を整える“マインドフルネス”
1日5分、呼吸に意識を向けるだけで副交感神経が働き、脳の過剰な活動を鎮めます。
③ プロの手で“体からアプローチ”
アロマトリートメントやヘッドケアで首・頭皮をほぐすと血流が改善。酸素が脳に行き渡り、情報処理がスムーズになります。
脳疲労が改善したお客様
40代女性Aさんは「仕事中に集中できず、寝ても疲れが取れない」と来店。
週1回のヘッドケアとアロマを取り入れた結果、1か月で「朝の目覚めがスッキリし、頭の重さが減った」と実感。
脳疲労が回復することで、心も前向きに変わっていきました。
脳のサインに気づいて!
「最近やる気が出ない」「頭がぼんやりする」――それは年齢のせいではなく、脳疲労のサインかもしれません。
ちゅ楽では、アロマトリートメントやヘッドケアで脳疲労をリセットし、心と体の両面から回復をサポートします。
その疲れを放置せず、今日から“脳に休息”をプレゼントしてみませんか?
(ちゅ楽)
2025年9月 3日 09:30





【腰痛に悩む人必見】その痛み、実は"脳と筋肉の誤作動"かもしれません

「腰が痛いのは年齢のせい」と思っていませんか?
「デスクワークで座りっぱなし」「立ち上がると腰がズキッと痛む」
そんな腰痛を「年齢だから仕方ない」と諦めていませんか?
実は、最新の研究では 腰痛の約8割が、骨や椎間板の異常ではなく“筋肉や神経の緊張”によるもの と言われています。
つまり、ただの「老化」や「持病」ではなく、ケアによって改善できる余地が大きい症状なのです。
腰痛の正体は「筋肉の緊張」と「脳の過剰反応」
腰痛の多くは「筋・筋膜性腰痛」と呼ばれるタイプ。
これは、筋肉や筋膜(筋肉を包む膜)が硬くなり、神経を圧迫して痛みを引き起こすものです。
さらに近年では、「脳の痛みの記憶」も腰痛に関係しているとわかってきました。
ストレスや不安で交感神経が優位になると、筋肉は緊張状態になり、脳は「痛みがある」と過敏に信号を出してしまうのです。
(ちゅ楽)
2025年9月 1日 08:51





不安で眠れない夜に|心を整えるためのストーリーと実践法

ある女性の物語
30代の女性Mさん。
仕事の責任が増え、夜になると「今日のあの発言はよかったのかな」「明日もうまくできるだろうか」
と考え込み、布団に入っても眠れません。
眠れないことで「また寝不足になって仕事に影響したらどうしよう」とさらに不安が膨らみ、朝を迎えるたびに疲れ切っていました。
不安が心と体に及ぼす影響
不安や緊張は、心だけでなく体にも症状をもたらします。
-
寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める
-
肩こりや首の重さ、頭痛
-
動悸や胃の不快感
-
集中力や判断力の低下
つまり、心の不安は「体の痛み」と「生活の質の低下」に直結してしまうのです。
Mさんの変化:専門的アプローチとの出会い
Mさんは「このままでは心も体も限界だ」と思い、リラクゼーションサロンに相談。
提案されたのは心と体を同時に整える習慣でした。
① 呼吸法の習慣化
深い呼吸で自律神経を整え、不安を鎮める。
② ボディケアで緊張を解放
肩・首のこりをほぐすことで、心の重さも軽くなる。
③ アロマで睡眠環境を整える
ラベンダーやニオイコブシなどリラックス効果のある香りを取り入れる。
物語の続き:半年後のMさん
最初の頃は半信半疑だったMさんですが、週1回のケアと毎日の小さな習慣を続けました。
すると少しずつ「夜に考え込みすぎなくなった」「寝ても翌朝スッキリ起きられる」など変化が現れました。
半年後には、以前は恐怖だったプレゼンの場でも落ち着いて話せるようになり、
プライベートでも「趣味を楽しむ余裕ができた」と話すように。
読者へのメッセージ
不安や緊張は誰にでもある自然な反応です。しかし、それが続くと心も体も疲弊し、人生そのものを重くしてしまいます。
だからこそ大切なのは、不安に振り回されないための心と体のケア。
呼吸・アロマ・ボディケアといったアプローチは、心を落ち着け、体をゆるめ、眠れる夜を取り戻す力になります。
そして、『ちゅ楽』で一番のおすすめはヘッドケアです!
ヘッドケアを受けてみるとわかりますが、整いました~♪って感じです(笑)
お客様の声
「夜中に何度も目が覚めていたのが、今ではぐっすり眠れるようになった」
「体の緊張がほぐれると、気持ちまで楽になると実感した」
「眠れるようになってから、職場の人間関係にも前向きに向き合えるようになった」
こうした声が示すように、心と体は切り離せないのです。
行動への一歩
不安や緊張で眠れない夜を、あなたは何度過ごしてきましたか?
放っておいても自然に解消するとは限りません。
ちゅ楽では、心と体を同時に整えるケアを通して、不安に振り回されない毎日をサポートしています。
もしあなたが「また眠れない夜が来るのでは…」と悩んでいるなら、今こそ行動を変えるタイミングです。
眠れる夜と、前向きに過ごせる日常を、一緒に取り戻していきましょう。
(ちゅ楽)
2025年8月31日 08:57





なぜ肩こりはなくならないのか?|慢性的な肩こりの原因と解決法

あなたもこんな悩みを抱えていませんか?
「毎日デスクワークで肩が重い」
「マッサージを受けてもすぐ戻る」
「最近は頭痛まで出てきた」
実は肩こりは、日本人の不調ランキングで常に上位。多くの人が悩んでいます。
ではなぜ、肩こりはこんなにも頑固で繰り返すのでしょうか?
なぜ肩こりは繰り返すの?
一時的にほぐしてもすぐ戻る肩こり。その理由は「原因が一つではない」からです。
-
長時間の同じ姿勢による筋肉の硬直
-
運動不足による血流の滞り
-
ストレスによる自律神経の乱れ
-
眼精疲労や歯の食いしばりなど、隠れた要因
つまり、単に肩の筋肉をもみほぐすだけでは根本的な改善にならないのです。
お客様の中にも同じ経験があります
お客様もかつて、デスクワークで毎日のように肩こりに悩んでいました。
どこの整体やマッサージに行っても、一瞬は軽くなるけれど、またすぐに重だるさが戻ってくる…。
「もうこれは体質だから仕方ないのか」と諦めかけていたこともあったそうです。
でも実際は、正しいケアと習慣を続けることで、あの頃のつらい肩こりから解放されました。
専門的な視点から見る解決法
① 姿勢改善が第一歩
肩こりの大きな原因は「猫背」と「前傾姿勢」。
スマホやPCを見るときに頭が前に出ると、首や肩に数倍の負担がかかります。
リリース整体で歪みをリセットし、日常では背骨を動かす意識が重要です。
② 血流を促すボディケア
筋肉が硬くなったままでは血液も流れにくく、疲労物質が蓄積します。
定期的に肩甲骨まわりをゆるめることで、血流と酸素供給が改善し、こりにくい状態をつくれます。
③ ストレスケアで自律神経を整える
肩こりは心の状態とも直結しています。
ストレスで交感神経が優位になると筋肉は硬直。
ヘッドケアや深呼吸、アロマを取り入れると、心身がゆるみ肩こりの悪循環を断ち切りやすくなります。
実際のお客様の声
「仕事終わりには毎日肩がパンパンでしたが、ボディケアを受けるようになって頭痛も減り、夜もぐっすり眠れるようになりました」
「リリース整体とセルフストレッチのアドバイスで、以前のように肩こりで仕事が手につかないことがなくなりました」
こうした声が示すように、体の外側だけでなく、生活全体のケアが肩こり改善には不可欠なのです。
あなたにできる行動ステップ
-
まずは自分の肩こりタイプを知る
姿勢が原因か?ストレスか?眼精疲労か?原因を意識することが解決の第一歩。
-
毎日の小さな習慣を変える
スマホを顔の高さで見る、1時間ごとに肩を回すなど、負担をためない生活習慣を取り入れる。
-
専門的なケアを受ける
セルフケアだけでは足りない部分を、リリース整体やボディケアでサポート。これにより改善がぐっと早まります。
一歩を踏み出す勇気
肩こりは「慢性だから仕方ない」と諦めがちですが、実は根本改善の余地が大きい症状です。
もし今「肩の重さで毎日がつらい」と感じているなら、ぜひ一度ご相談ください。
ちゅ楽では、ボディケア、リリース整体で姿勢・筋肉・心の緊張を同時にリリースするアプローチを行っています。
あなたの肩こりも、しっかりとケアすれば必ず変わります。
(ちゅ楽)
2025年8月30日 09:38





繰り返す腰痛に悩むあなたへ|ぎっくり腰を防ぐためのボディケアとリリース整体の大切さ

朝起きた瞬間に腰が重だるい。椅子から立ち上がるときにズキッと痛みが走る。荷物を持ち上げた拍子に腰を痛めてしまう。
いつもブログを読んでくださり、ありがとうございます。
今日は、腰痛についてです。
腰痛は、とても多い症状のひとつです。
腰痛の方の参考になれば嬉しいです♪
「また腰が痛い…」とため息をついていませんか?
朝起きた瞬間に腰が重だるい。椅子から立ち上がるときにズキッと痛みが走る。荷物を持ち上げた拍子に腰を痛めてしまう。
こうした腰痛の悩みは、多くの方にとって日常的な問題です。
特に「ぎっくり腰」を経験したことがある人は、その再発が常に頭をよぎり、
不安と隣り合わせの生活を送っているのではないでしょうか。
腰痛を放置するとどうなるのか?
腰痛は単なる「一時的な痛み」ではなく、放置すれば悪循環を生みます。
-
痛みをかばうことで姿勢が崩れ、筋肉のバランスがさらに悪化
-
運動不足になり、血流や代謝が落ちて疲れやすい体に
-
精神的にも「また痛くなるかも」という不安が募り、活動量が減る
-
重度になると椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症といった疾患につながる可能性も
このように、腰痛は体だけでなく心や生活の質にまで影響を与えます。
腰痛は放置せずに、対処していきましょう!
腰痛を防ぎ、快適に動ける体をつくる3つの方法
1. 生活習慣の見直し
長時間のデスクワークやスマホ操作は、腰に大きな負担をかけます。
こまめに立ち上がって体を動かす、座るときは骨盤を立てる意識を持つ、
といった小さな工夫で腰の負担を軽減できます。
2. セルフケアで筋肉を守る
腰痛は腰だけでなく、お尻や太ももの筋肉の硬さとも関係しています。
ストレッチや軽い運動を取り入れることで筋肉の柔軟性を保ち、再発を防ぐ効果が期待できます。
3. プロのケアで根本改善を目指す
セルフケアだけでは解消できない深いコリや歪みには、専門の施術が有効です。
ちゅ楽では、ボディケア、リリース整体などで、筋肉の緊張を解きほぐしながら骨格のバランスを整えます。
これにより一時的な痛みの緩和だけでなく、腰痛の「原因」にアプローチできるのです。
つまり、骨盤・背骨・股関節が大きく関係しています。
実際のお客様の声
「何度もぎっくり腰を繰り返していましたが、リリース整体を受け始めてからは腰の安定感が出て、再発が減りました。」
「長年のデスクワークで腰が固まっていたのですが、施術の後は体が軽く、歩くのが楽になりました。」
「整体だけでなく、自宅でできるセルフケア方法も教えてもらえたので安心感があります。」
腰痛の不安を手放して、動ける毎日へ
腰痛は「仕方ない」と我慢するものではありません。
適切なケアを受けることで再発を防ぎ、快適に動ける体を取り戻すことができます。
ちゅ楽では、ボディケア、リリース整体で腰痛の根本原因にアプローチし、再発予防までサポートしています。
「またぎっくり腰になるのでは…」と不安を抱えている方こそ、今のうちにしっかりとケアを始めることが大切です。
まだ諦めてはいけません!
一緒に、腰痛に向き合いましょう!
行動を起こすのは「今」
腰痛をそのままにしてしまうと、気づかないうちに生活全体の質を下げてしまいます。
「まだ大丈夫」と思っている今こそ、将来の体を守るチャンスです。
不安を手放し、腰から自由になる毎日を手に入れましょう。
ちゅ楽がそのお手伝いをいたします。
ご来店お待ちしております。
(ちゅ楽)
2025年8月29日 10:41





不安に押しつぶされそうなときにできること|心を整えるメンタルケア

「理由はないのに、なんだか不安」そんな日ありませんか?
夜眠る前、突然不安な気持ちが押し寄せてきて眠れなくなる。
何か新しいことを始めようとするたびに「自分には無理かも」と心配になる。
こうした感情は誰にでもありますが、毎日のように続くと心も体も疲れてしまいます。
不安は決して弱さの証ではなく、人間にとって自然な感情です。
しかし、強すぎる不安を放置すると生活の質が下がり、心身の不調につながってしまいます。
不安を放置すると起こる悪循環
不安感は心だけでなく体にも影響します。
-
頭痛や肩こり、胃の不快感など身体症状を引き起こす
-
集中力が落ちて、仕事や勉強の効率が下がる
-
イライラや焦燥感から人間関係のトラブルにつながる
-
睡眠の質が下がり、疲労感が抜けない
このように、不安は「気持ちの問題」ではなく、日常生活全体をむしばむ大きな要因になるのです。
不安を和らげる3つのメンタルケア
1. 呼吸を整える
不安を感じているとき、人は呼吸が浅くなりがちです。
意識して深い呼吸を行うことで、副交感神経が働き、心が落ち着いてきます。
1日数分の腹式呼吸を取り入れるだけでも違いを実感できます。
2. 自己肯定感を育てる習慣
「できていないこと」に意識を向けると不安は強まります。
逆に「今日できた小さなこと」を書き出すと、自己肯定感が育ち、不安に強くなれます。
日記や感謝ノートは、心の安定に効果的な習慣です。
3. プロの手によるリラクゼーション
体をほぐすケアは心の緊張を解く大きなサポートになります。
アロマトリートメントやヘッドケアなどで副交感神経を優位にすると、自然と不安が和らぎます。
心と体はつながっているため、身体を整えることは心を整える第一歩でもあるのです。
実際のお客様の声
「夜になると不安で眠れなかったのですが、アロマの香りに包まれて施術を受けた後はぐっすり眠れました。」
「自分に自信がなく不安が多かったのですが、通ううちに気持ちが前向きになり、以前より笑顔が増えました。」
「ボディケアを受けて体が楽になると、心まで軽くなった感覚があります。体と心はつながっていると実感しました。」
一歩踏み出すことで不安は軽くなる
不安は「なくすもの」ではなく「小さくして付き合っていくもの」です。
そのためには、自分の心の状態を理解し、整える方法を知ることが大切です。
ちゅ楽では、体だけでなく心に寄り添うケアを大切にしています。
ボディケアやアロマトリートメントを通じて、リラックスした状態を取り戻すお手伝いをしています。
「不安に押しつぶされそう…」と感じたときは、一人で抱え込まず、ぜひ心と体を整える時間をつくってみてください。
(ちゅ楽)
2025年8月27日 10:32





慢性的な頭痛に悩む方へ|心身から整えるボディケアの重要性

「また頭が痛い…」そんな毎日を繰り返していませんか?
頭痛に悩まされる方はとても多く、「日本人の約4人に1人」が慢性的な頭痛を抱えていると言われています。
頭全体が重く締め付けられるように痛むこともあれば、ズキズキとした片頭痛に悩まされる方も。
市販薬でやり過ごしても、またすぐに繰り返してしまう…。
「病院に行くほどでもないけどつらい」「頭痛薬に頼りたくない」
そんなお悩みを抱えている方は少なくありません。
頭痛を放置するとどうなる?
頭痛は単なる不調ではなく、体と心からのSOSです。そのままにしておくと、次のような悪循環に陥ります。
-
集中力や思考力の低下 → 仕事や勉強の効率が下がる
-
イライラや気分の落ち込み → 人間関係にも影響
-
首こり・肩こりの慢性化 → 姿勢の悪化や自律神経の乱れ
-
睡眠の質の低下 → 疲労が抜けず、さらに頭痛が悪化
つまり、頭痛を「ただの不調」として軽く考えると、日常生活の質を大きく損なってしまうのです。
頭痛を和らげる3つのアプローチ
1. 首・肩まわりの筋肉をゆるめる
緊張性頭痛の多くは、首や肩の筋肉が硬くなり、血流が滞ることで起こります。
ボディケアやリリース整体で筋肉の緊張をほぐすことで、頭への血流がスムーズになり、痛みの軽減が期待できます。
2. 自律神経を整える
頭痛はストレスや自律神経の乱れとも深く関係しています。
ヘッドケアやアロマトリートメントを組み合わせることで副交感神経が優位になり、心が落ち着き、痛みを感じにくい体に導きます。
3. 姿勢改善とセルフケア
長時間のデスクワークやスマホ操作で猫背やストレートネックになると、頭の重みを首や肩が支えきれず頭痛を悪化させます。
施術だけでなく、自宅でできる簡単なストレッチや呼吸法を取り入れることも効果的です。
実際のお客様の声
「慢性的な頭痛で薬が手放せなかったのですが、ボディケアとヘッドケアを受けた日から頭が軽くなり、薬の使用が減りました。」
「アロマトリートメントを受けると、不思議と心も落ち着いて頭痛が和らぎます。眠れるようになったのも嬉しいです。」
「定期的に通うようになってから、頭痛だけでなく肩こりも改善。仕事の集中力が戻ってきました。」
こうした声が示すように、頭痛は「我慢するもの」ではなく、適切なケアで改善が期待できる症状なのです。
行動を変えれば、頭痛のない日常が戻ってくる
頭痛は決して「ただの体質」や「仕方ないこと」ではありません。
体と心の両面からアプローチすることで、頭痛の頻度や強さを減らすことが可能です。
ちゅ楽では、ボディケア・リリース整体・ヘッドケア・アロマトリートメントなどを組み合わせ、
お客様一人ひとりの症状に合わせたケアをご提案しています。
「また頭が痛くなるのでは…」という不安から解放され、安心して毎日を過ごすために。
ぜひ一度、ちゅ楽の施術を体験してみてください。
(ちゅ楽)
2025年8月26日 09:12





眠れないときのメンタルケア|心と体を整える習慣

「寝たいのに眠れない…」そんな夜はありませんか?
布団に入ってもなかなか眠れない、夜中に何度も目が覚めてしまう。
朝起きてもぐっすり眠れた感じがしない。そんな経験をしたことは、多くの方にあるのではないでしょうか。
一晩眠れないだけでも翌日がつらいのに、それが続いてしまうと「ちゃんと眠れない自分」に不安を感じてしまい、
さらに眠れなくなるという悪循環に陥ってしまいます。
眠りの悩みは、ただの「寝不足」ではなく、心と体の両方に大きな影響を与える深刻な問題なのです。
放置すると心身にさまざまな影響が
「眠れない」状態が続くと、心と体にこんな悪影響があります。
-
集中力や判断力が低下し、仕事や勉強に支障が出る
-
イライラしやすくなり、人間関係がギクシャクする
-
自律神経のバランスが崩れ、肩こりや頭痛、胃腸の不調を招く
-
気分の落ち込みが強くなり、うつ状態に発展することも
つまり「眠れない夜を放置する」ことは、心身の健康を少しずつ削っていく行為といえるのです。
眠れないときに試したい心のケア
眠りの質を高めるためには、ただ体を休めるだけでなく「心を安心させる」ことが欠かせません。
ここでは、すぐに取り入れられる3つの習慣をご紹介します。
1. 一日の終わりに「頭の中を空っぽにする」
眠れない原因のひとつは、考えごとが止まらないこと。
そんなときは、寝る前に紙に不安や予定を書き出してみましょう。
「頭の中から外に出す」ことで気持ちが整理され、脳が休む準備を始めます。
2. 呼吸で自律神経を整える
深い眠りには副交感神経が優位になることが大切。
ベッドに入ったら「4秒吸って、6秒吐く」呼吸を繰り返してみましょう。
呼吸に意識を向けることで自然とリラックスし、眠りにつながりやすくなります。
3. 香りで脳に「眠る合図」を送る
アロマの香りは脳に直接届き、心の状態を変えてくれます。
ラベンダーやニオイコブシなどの香りは「眠る準備」を促す効果があり、安心感に包まれながら入眠しやすくなります。
ちゅ楽のアロマトリートメントでも、こうした香りを活かしたケアを行っています。
「眠れるようになった」お客様の声
実際に眠れない夜に悩んでいたお客様からは、こんなお声をいただいています。
・「仕事のストレスで夜中に目が覚めることが多かったのですが、
ボディケアとヘッドケアを受けた日は自然に眠れて、朝までぐっすり。久しぶりにスッキリ目覚めることができました。」
・「アロマトリートメントを受けた後は、気持ちが落ち着いて『眠れる自分』を取り戻せました。
今は寝る前にアロマを焚く習慣を取り入れています。」
眠りの質が変わることで「日中の集中力が戻った」「イライラが減った」といった心身の変化を実感される方も多いのです。
「眠れない夜」を一人で抱え込まないで
眠れないとき、私たちはつい「自分が弱いから」と責めてしまいがち。
でも、眠れないのは弱さではなく、心と体が「助けて」とサインを出している証拠です。
ちゅ楽では、ボディケア・ヘッドケア・アロマトリートメントなどを通じて、
心と体の両面から「安心して眠れる状態」へと導いていきます。
行動を変えることで、眠りも変わる
今の「眠れない夜」を当たり前にしないでください。
ほんの少しの工夫と、専門的なケアを取り入れることで、眠りは必ず変わります。
「眠れない夜がつらい」と感じたら、ぜひちゅ楽にご相談ください。
心と体をゆるめることで、あなたの眠りをサポートさせていただきます。
(ちゅ楽)
2025年8月23日 09:32





<<前のページへ|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|次のページへ>>
« ちゅ楽について | メインページ | アーカイブ | 【BIOLAB】商品について »