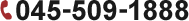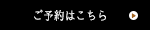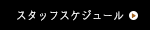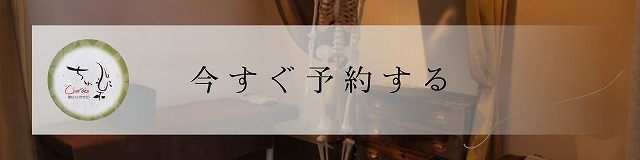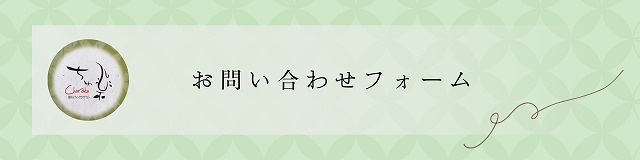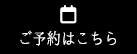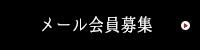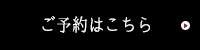カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2026年2月 (5)
- 2026年1月 (15)
- 2025年12月 (26)
- 2025年11月 (29)
- 2025年10月 (31)
- 2025年9月 (30)
- 2025年8月 (25)
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (3)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (3)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (6)
- 2024年3月 (7)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (5)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (3)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (5)
- 2023年5月 (8)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (10)
- 2023年2月 (10)
- 2023年1月 (27)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (2)
- 2022年7月 (3)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (5)
- 2021年4月 (4)
- 2021年3月 (10)
- 2021年2月 (7)
- 2021年1月 (5)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (6)
- 2020年9月 (6)
- 2020年8月 (9)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (3)
- 2020年5月 (4)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (3)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (7)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (5)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (5)
- 2019年7月 (8)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (9)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (4)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (8)
- 2018年9月 (3)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (7)
- 2018年3月 (6)
- 2018年2月 (9)
- 2018年1月 (8)
- 2017年12月 (12)
- 2017年11月 (9)
- 2017年10月 (13)
- 2017年9月 (15)
- 2017年8月 (19)
- 2017年7月 (12)
- 2017年6月 (16)
- 2017年5月 (8)
- 2017年4月 (20)
- 2017年3月 (14)
- 2017年2月 (7)
- 2017年1月 (11)
- 2016年12月 (6)
- 2016年11月 (7)
- 2016年10月 (9)
- 2016年9月 (5)
- 2016年8月 (4)
- 2016年7月 (8)
- 2016年6月 (6)
- 2016年5月 (16)
- 2016年4月 (9)
- 2016年3月 (10)
- 2016年2月 (10)
- 2016年1月 (8)
- 2015年12月 (7)
- 2015年11月 (10)
- 2015年10月 (13)
- 2015年9月 (8)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (15)
- 2015年6月 (17)
- 2015年5月 (16)
- 2015年4月 (20)
- 2015年3月 (18)
- 2015年2月 (14)
- 2015年1月 (6)
- 2014年12月 (3)
- 2014年11月 (9)
- 2014年10月 (9)
- 2014年9月 (8)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (13)
- 2014年5月 (11)
- 2014年4月 (12)
- 2014年3月 (5)
- 2014年2月 (7)
- 2014年1月 (10)
- 2013年12月 (6)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (6)
- 2013年9月 (7)
- 2013年8月 (5)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (8)
- 2013年5月 (5)
- 2013年4月 (6)
- 2013年3月 (4)
最近のエントリー
HOME > スタッフブログ > 体について > 11月も終わりに近づき、もうすぐ12月。心と体が"変わり目"を迎える時期にやっておきたいこと
スタッフブログ
< 心の疲れがとれる場所 ―「感じないまま頑張ってきたあなたへ」ちゅ楽が届けたいこと | 一覧へ戻る | 膝の痛み(変形性膝関節症)──「年齢のせい」だけではない、回復のチャンスはまだある >
11月も終わりに近づき、もうすぐ12月。心と体が"変わり目"を迎える時期にやっておきたいこと

11月も終わりに近づき、街の空気がぐっと冷たくなってきました。
夕方の暗くなる時間も早くなり、気づけば「今年もあと少し」。
12月の予定を立て始めている方も多いのではないでしょうか。
この“11月末〜12月”は、心と体にとって大きな 季節の変わり目。
気温・湿度・日照時間・生活リズム…すべてが変化し、その影響は体に素直に現れます。
実際、ちゅ楽でもこの時期は毎年、
-
朝起きても疲れが抜けない
-
頭が重い・目が疲れる
-
肩こりや背中のハリが強くなる
-
呼吸が浅い
-
なんとなく気持ちが焦る
というご相談が一気に増えてきます。
なぜこの時期に不調が増えるのか?
そして、12月を元気に乗り切るために何をしておくべきか?
今日は 心と体が冬モードに切り替わる11月末だからこそやるべきケアをお伝えします。
1. 11月末は「自律神経」が最も乱れやすい季節
11月の終わりは、体がまだ“秋モード”のままなのに、環境はすでに“冬モード”。
このギャップを埋めようと、自律神経がフル回転します。
特に影響が大きいのは、
-
朝晩の急な冷え
-
日照時間の短さ(=脳の疲労)
-
年末の心理的プレッシャー
これらが重なることで、交感神経が働きすぎてしまいます。
交感神経が強すぎると、
-
筋肉が固まる
-
呼吸が浅くなる
-
眠りが浅くなる
-
脳の疲れが取れない
という「冬の不調」がスタートします。
つまり、11月末は 冬の不調が始まる“ゼロ地点” といえるのです。
2. 冬の不調の入口は「脳疲労」と「巡りの低下」
この時期に増えるお悩みの根本は、
-
脳疲労
-
血流低下
-
寒さによる筋膜の硬さ
この3つです。
スマホ・パソコンの負荷も冬は上がります。
特に朝の冷え込みが強いと、筋肉や筋膜が固まるため、同じスマホ操作でも 肩・首・背中にかかる負担が倍増 します。
「首こり → 眼精疲労 → 脳疲労 → 自律神経の乱れ」
この負のループが起こりやすいのが11月〜12月なのです。
3. 12月をラクに乗り切るために
やっておきたい3つのケア
① 首・背中を“冬に強い状態”にする
この時期は背中〜肩甲骨周りが固くなりやすいので、
-
肩甲骨の可動域を広げる
-
背中の筋膜の張りをほどく
-
首の前後のバランスを整える
この3つが最重要。
固まったまま12月に突入すると、一気に疲れが溜まり、年末にダウン… というケースが本当に多いです。
ちゅ楽の「リリース整体」では、冬になると特に大きく動きが悪くなる“胸椎の可動域”を丁寧に開いていくことで、
呼吸が深くなり、脳疲労も軽減します。
② 脳疲労ケアを早めに始める
冬は脳が疲れやすい季節。
理由は「光の量が減る」からです。
光が減ると脳はリラックスホルモンを作りにくく、交感神経の緊張が高まり続けます。
おすすめは、
-
早い時間に太陽光を浴びる
-
夜のスマホは30分早く切る
-
目の周りを温める
そして、ちゅ楽では 頭・首のリリース+自律神経調整 を組み合わせて、脳の疲れを深部から解除していきます。
脳疲労をそのままにして12月に入ると、一気に疲れが溜まるので「今のうちのケア」がとても大切です。
③ 体温を“上げる力”を取り戻す
冬は血流が命。
血流が落ちると、
-
むくむ
-
筋肉が固まる
-
代謝が落ちる
-
冷えが深刻化する
など、さまざまな不調につながります。
インディバはこの季節に非常に相性が良く、
-
深部加温で体の芯から温まる
-
自律神経が整いやすい
-
眠りの質が高まる
-
筋膜が緩みやすい
というメリットが重なります。
整体との組み合わせで「巡りの良い冬の身体」をつくっておくのがおすすめです。
4. 11月末は“身体の仕込み期間”。
12月の元気はここで決まる
12月はどうしてもスケジュールが詰まりやすく、ケアの時間を取れなくなります。
だからこそ、11月末〜12月最初の1〜2週間は “冬本番に向けての調整期間” として過ごすのが理想です。
-
仕事の負荷
-
スマホ時間
-
気温の低下
-
生活リズムの乱れ
すべてのストレスが積み重なる前に、体を整えておくことで、
✔ 疲れの溜まり方が全然違う
✔ 年末も心に余裕ができる
✔ 12月の忙しさに振り回されない
という“冬の強さ”が手に入ります。
ちゅ楽は、この季節の変わり目に合わせて、
-
リリース整体
-
インディバ
-
自律神経調整
-
眼精疲労ケア
-
深部筋・筋膜のアプローチ
お客様の状態に合わせた「冬モードの施術設計」を行っています。
「今年は疲れを溜め込みたくない」
「12月を元気に過ごしたい」
そんな方は、ぜひこのタイミングで一度整えてみてください。
あなたの冬が少しでも軽く、あたたかくなりますように。
カテゴリ:
(ちゅ楽) 2025年11月26日 07:43
< 心の疲れがとれる場所 ―「感じないまま頑張ってきたあなたへ」ちゅ楽が届けたいこと | 一覧へ戻る | 膝の痛み(変形性膝関節症)──「年齢のせい」だけではない、回復のチャンスはまだある >
同じカテゴリの記事
膝の痛み(変形性膝関節症)──「年齢のせい」だけではない、回復のチャンスはまだある

「歩き始めが痛い」
「階段の上り下りがつらい」
「立ち上がる時に膝がギシギシする」
11月から冬にかけては、膝の痛みを訴える方が一気に増える季節です。
特に多いのが、変形性膝関節症による“ズキッとした痛み”や“重だるさ”。
しかし、実は膝の痛みの多くは「変形そのもの」より “周辺の筋肉・関節の動きの悪さ” によって悪化しています。
つまり、適切なケアを行うことで「まだ十分に回復の余地がある」ということです。
■ 変形性膝関節症の本当の原因は
「膝以外」にあることが多い
膝が痛いと、人は膝だけを気にします。しかし、膝は“全身のバランスの受け皿”。
以下の原因が積み重なることで膝に負担が集中します。
● 太ももの筋膜の癒着
太もも(大腿四頭筋)の硬さは、膝蓋骨の動きを妨げ、曲げ伸ばしのたびに痛みを生みます。
● 股関節の動きの悪さ
股関節が動かないぶん、膝が余計に動かされて負担が倍増します。
● 足裏アーチの崩れ
外反母趾・偏平足は膝の角度をズラし、軟骨のすり減りを加速させます。
● 冷えによる筋緊張
深部体温の低下は、膝周りの循環を落とし、痛みを強く感じさせます。
実際、ちゅ楽に来られる膝痛のお客様の多くが、
「膝以外の施術をしたら痛みが軽くなった」
と驚かれます。
■ なぜ“治らない膝痛”が多いのか?
理由はシンプルです。
膝だけにアプローチしているから。
湿布・注射・電気治療は痛みを一時的に抑えることはできますが、
・股関節の動き
・太ももの筋緊張
・足裏の崩れ
など、“根本原因”に働きかけられません。
本当に必要なのは、
膝に負担をかけている原因を取り除き、膝がラクに動ける環境を整えること。
そのために最適なのが、ちゅ楽の リリース整体・インディバ・ボディケア の組み合わせです。
■ ちゅ楽が膝痛改善に強い理由
① 深部の筋膜・関節の動きを整える「リリース整体」
膝痛の鍵は「大腿四頭筋・ハムストリング・腸腰筋」。
ここが硬いと膝が常に引っ張られ、痛みが悪化します。
リリース整体では、
・筋膜の癒着
・関節の“引っかかり”
・動きのクセ
にアプローチし、“痛みが出ない動き方”へ導きます。
② インディバで膝周りの循環・修復力を高める
インディバの高周波(448kHz)は、膝関節の深部まで熱を届け、
・炎症の緩和
・軟部組織の修復
・筋肉の柔軟性UP
に非常に効果的です。
特に、膝内側の痛み・腫れ・動かした時のギシギシ感には相性抜群。
③ ボディケアで負担の分散をつくる
膝だけに頼りすぎていた動きを、
・腰
・股関節
・太もも
・足裏
が分散して支えられるようにします。
これにより、膝“だけ”が頑張る状態から解放されます。
■ 変形が進んでいても、できることはある
「変形があるから…」
「軟骨がすり減っていると言われた」
と諦める必要はありません。
実際には、
変形=痛みの強さ ではありません。
動きや筋膜が整えば、
・痛みが減る
・立ち上がりやすい
・歩きやすい
・階段がラク
といった改善は十分に可能です。
これは、長年施術をしてきた経験から断言できます。
■ 痛みが強い今こそ、ケアの始めどき
もし今、
✔ 歩き始めが痛む
✔ 朝のこわばりが強い
✔ 階段がつらくなってきた
✔ 膝に水がたまりやすい
✔ マッサージではすぐ戻る
こんなサインが出ているなら、膝が“限界の手前”まで来ている証拠です。
早めにアプローチすれば、改善のスピードは確実に早くなります。
■ 最後に ── 膝は「人生の質」を左右する
膝が痛いだけで、
・出かけるのが嫌になる
・家事がつらくなる
・趣味を諦める
・自信がなくなる
気持ちまで沈んでしまう方を、私はたくさん見てきました。
だからこそ、
膝が軽くなる=人生が軽くなる。
変形があっても、年齢を重ねていても大丈夫。
あなたの膝が再び動きやすくなるように、ちゅ楽は全力でサポートします。
いつでもご相談ください。
あなたの膝は、まだまだ良くなります。
(ちゅ楽) 2025年11月27日 07:18
心の疲れがとれる場所 ―「感じないまま頑張ってきたあなたへ」ちゅ楽が届けたいこと

最近、こんなお悩みを耳にすることが増えました。
-
とにかくやる気が出ない
-
疲れているのに眠れない
-
頭ばかり冴えて体がついてこない
-
休んでいるのに休めた感じがしない
-
気持ちが落ち着かず常に緊張している
これらは身体の問題というより、“心の疲れ” が限界に近づいているサインです。
そして、多くの人は気づかないまま、毎日を何とかやり過ごしてしまいます。
■ 心の疲れは、静かに、深く、
気づかれずに進んでいく
心の疲れは、筋肉のように「痛い」「重い」と教えてくれません。
むしろ、静かに忍び寄ります。
-
仕事中に深呼吸が増えた
-
思考がネガティブ寄りになる
-
小さなことでイライラや不安が出る
-
楽しかったはずのことに興味がわかない
リラックスの仕方を忘れ、交感神経が過剰に働き続けると、体の症状として現れはじめます。
-
背中が張る
-
呼吸が浅い
-
頭痛やめまい
-
首や肩の強いこり
-
腸の不調
-
眠れない・すぐ目が覚める
多くの人が「体の問題」だと思い施術を受けますが、根本は 心の緊張 による自律神経の乱れであることが非常に多いのです。
■ 心とカラダは分けられない ―
“癒し” の本質は、自律神経を整えること
ちゅ楽の施術の根底には、
「心と体はひとつのもの」
という考えがあります。
整体で体を整えても、
アロマで筋肉を緩めても、
ヘッドケアで頭をほぐしても、
結局、心の緊張が抜けていなければ、また同じ不調に戻ってしまう。
だからこそ、ちゅ楽では
筋肉だけ、関節だけ、神経だけ
のアプローチではなく、
✔ 心の緊張をほどき
✔ 自律神経を整え
✔ 呼吸が深くなる体
に導くことを最も大切にしています。
■ 心の疲れに効果的な“4つのケア”
― ちゅ楽のメニューはすべて「心をゆるめる」ためにある
① 脳疲労ケア(ヘッドケア) ― 心の騒がしさが静まる
現代人は常に頭を使い続けています。
-
情報過多
-
SNS
-
仕事のタスク
-
人間関係の気遣い
脳が休まらないため、気持ちが落ち着かないまま。
脳疲労ケアは、
頭皮・側頭筋・後頭下筋群をじっくり緩めることで、
-
不安・緊張が抜けていく
-
呼吸が自然と深くなる
-
眠りやすくなる
-
思考が軽くなる
という “心の静けさ” を取り戻すケアです。
② アロマトリートメント ― 香りで心がほどける瞬間
アロマは筋肉を緩めるだけではありません。
香りは脳の“感情をつかさどる部分(扁桃体)” にダイレクトに届き、
自律神経やホルモンバランスに作用します。
-
「考えすぎる癖が止まらない」
-
「寝てもスッキリしない」
-
「気持ちが落ち込む」
こういう時こそ、アロマが効果を発揮します。
ちゅ楽ではその日の心身の状態に合わせてブレンドするため、
施術が終わる頃には “心の重さがふっと消える” と感じる方が多いです。
③ リリース整体 ― 心の緊張まで抜けていく整体
痛みのためではなく、
呼吸が通る体・しなやかに動ける体 を作る整体。
深層筋・筋膜・関節にアプローチしながら、
同時に“神経の流れ” を整えていきます。
実は、心が疲れている人ほど背骨・肋骨の動きが固くなるため、
-
呼吸が浅い
-
背中が張る
-
ため息が増える
といった状態が続きます。
リリース整体では、
心身を縛っていた「緊張のクセ」を解いていくため、
施術後にスッキリした
という方も少なくありません。
④ インディバ ― 心の“張りつめたスイッチ”がOFFになる深部温熱
インディバは、体を温めるだけの機器ではありません。
深部の血流と細胞の回復が高まり、
神経の過緊張が緩むことで、
-
心のざわつきが静まる
-
胃腸の働きが良くなる
-
疲労感が消えていく
といった効果があります。
何をしても疲れが抜けない人は、
体ではなく 心のエネルギーが枯渇している状態 かもしれません。
■ 心が疲れていると、人生の景色まで暗くなる
心の疲労が続くと、
-
できていたことができなくなる
-
大切な人に優しくできない
-
夢や目標が見えなくなる
-
自分を責めてしまう
こんな悪循環に入ります。
心がしんどいまま頑張り続ける必要はありません。
ちゅ楽は、
「体を治す場所」
である前に、
“心が還ってこれる場所”
でありたいと思っています。
■ 心の疲れは、
自分ひとりでは回復しきれないことがある
ストレス社会で生きる私たちは、
「気合い」や「休めば治る」では追いつかないほど
心の負担を抱えています。
だから、
誰かの手を借りていい。
あなたは悪くない。
そして、
施術によって呼吸が深まり、
心がふっと軽くなった瞬間、
本来のあなたの力が戻ってきます。
■ 最後に
もし今、
-
気持ちが晴れない
-
疲れているのに眠れない
-
何も楽しく感じられない
-
頭がいつも疲れている
-
心の余裕がない
そんな状態に心当たりがあるなら、
どうか一度、心を休めに来てください。
ちゅ楽の施術は、
体だけでなく 心の再生 を目的としています。
あなたがまた軽やかに動き出せるように。
そのお手伝いができたら嬉しく思います。
(ちゅ楽) 2025年11月25日 07:13
股関節の柔軟性を高める具体的ストレッチ&日常習慣

〜体が軽くなる、歩きやすくなる、疲れにくくなる〜
「最近、足が上がりにくい」「歩くと股関節の付け根がつまる」「開脚がぜんぜん広がらない」
――こうした悩みは、30代〜60代の女性にとても多く見られます。
特に青葉台エリアでも、デスクワークや車移動が多い方は股関節が固まりやすく、
腰痛・膝痛・姿勢の崩れにつながるケースが増えています。
股関節が硬くなると、次のような影響が出やすくなります。
-
歩幅が狭くなる
-
お尻の筋肉が使えず、太もも前だけが張る
-
骨盤が後ろに倒れ、猫背になりやすい
-
疲労が抜けにくい
-
むくみ・冷えが悪化する
つまり「股関節の硬さ」は、美容にも健康にもかなりの悪影響を与える大きな要因なのです。
今回は、自宅でできるストレッチや、日常生活で股関節をしなやかに保つための習慣を、
整体院の視点から分かりやすく解説します。
■ そもそも、なぜ股関節は固くなるのか?
股関節が固くなる原因は一つではありません。主に以下の4つが代表的です。
① 座りすぎ(股関節がずっと折れ曲がった状態)
座位姿勢が長いと、腸腰筋や大腿四頭筋が短縮し、股関節の動きが圧倒的に悪くなります。
② お尻の筋肉が使えていない
中殿筋・大殿筋が弱くなると、太もも前ばかりに負担がかかり、股関節が硬くなる悪循環に。
③ 骨盤の歪み・反り腰・猫背など姿勢的なクセ
姿勢が崩れると、股関節に本来とは違う方向の負荷がかかります。
④ 運動不足・可動域の減少
動かさない関節は、必ず動かなくなります。可動域は“自然減”するもの。
■ 今日からできる!
股関節を柔らかくするストレッチ
◎ ① 股関節ぐるぐる回し(基本の可動域アップ)
-
足を肩幅に開いて立つ
-
片足を大きな円を描くように前→外→後ろ→内へ回す
-
各10回ずつ
→ 関節液が循環し、滑らかに動きやすくなります。
◎ ② お尻(臀筋)ストレッチ
-
椅子に座り、片足を反対の膝に乗せる
-
背筋を伸ばしたまま前にゆっくり倒れる
-
お尻の外側が伸びるところで20〜30秒キープ
→ 股関節のつまりの大きな原因“梨状筋の硬さ”に効果的。
◎ ③ もも裏(ハムストリングス)ストレッチ
-
片足を前に出し、つま先を上げる
-
お尻を後ろに引くようにして前屈
-
太もも裏に伸びを感じながら20秒
→ ここが柔らかくなると、骨盤が正しい位置に戻りやすくなります。
◎ ④ 腸腰筋ストレッチ(反り腰・歩幅改善)
-
片膝をついてランジ姿勢
-
骨盤を軽く前に押し出す
-
前側の付け根が伸びる位置で20秒キープ
→ 歩く時の“足の出やすさ”が変わります。
■ 今日から意識できる
「股関節に良い日常習慣」
① 座りっぱなしを避ける(30〜60分に1回立つ)
立って足踏みするだけでもOK。股関節のつまりを防ぎます。
② 歩く時に“お尻を使う”意識を
・かかとから着地
・お尻で地面を押すイメージ
これだけで股関節がスムーズに。
③ 階段は“股関節を使って上がる”
太もも前ではなく、お尻と内ももを意識すると、自然と可動域が広がります。
④ お風呂で軽くマッサージ
太もも前、内もも、お尻を5〜10回なでるだけで血流改善。
■ それでも改善しない方へ ―
プロの施術が必要なケース
✔ 股関節の付け根が“鋭く痛い”
✔ 片側だけ強い違和感が続く
✔ 何ヶ月もストレッチしても変化がない
✔ 腰痛・膝痛を同時に感じる
これらは、「筋膜の癒着」や「骨盤の左右差」「深層筋の拘縮」が原因となっている可能性が高い状態です。
青葉台の ちゅ楽 では、
-
リリース整体(筋膜の癒着を丁寧にほどく)
-
ボディケア(血流と筋バランス調整)
-
アロマトリートメント(自律神経の安定)
-
インディバ(深層部の温熱で可動域改善)
を組み合わせて、股関節が“スッと動き出す”状態を目指します。
多くの方が施術後に
「脚の重さが消えた!」
「歩きやすい!」
「階段が楽になった!」
と変化を実感されています。
■ まとめ ― 今日からでも股関節は変わる
股関節の柔軟性は、年齢ではなく“使い方と習慣”で決まります。
毎日の小さなストレッチが、姿勢・歩き方・疲れ方まで大きく変えてくれます。
そして、セルフケアで限界を感じたら、専門家の施術を頼ることで、改善スピードは一気に上がります。
「股関節を柔らかくしたい」
「足が軽い体になりたい」
「姿勢を整えたい」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。
ちゅ楽は、あなたの体が本来持つしなやかさを引き出します。
(ちゅ楽) 2025年11月24日 07:59
股関節のつまり ― 放置すると体全体に影響!原因とセルフケア法

「最近、歩くと股関節が固まって動きにくい」「階段の上り下りで違和感がある」――
股関節のつまりは、多くの人が感じる不調ですが、放置すると腰痛や膝痛、姿勢の崩れ、疲労感につながります。
特に30代〜50代の女性は、筋力低下や生活習慣によって股関節の柔軟性が失われやすく、体の動き全体に影響を与えることがあります。
股関節のつまりの原因
股関節は体重を支える重要な関節であり、骨盤と脚をつなぐ役割を持ちます。
ここが硬くなる原因は主に以下の通りです。
-
筋肉のこわばり
大腿四頭筋、ハムストリングス、内転筋、臀筋などの柔軟性が低下すると、
股関節の可動域が狭くなり、歩行や日常動作で違和感が出ます。 -
骨盤の歪み・姿勢の崩れ
骨盤が後傾・前傾すると股関節の動きが制限され、腰や膝に負担がかかることで慢性的な痛みの原因となります。 -
関節の動きの不足
座りっぱなしや運動不足は股関節周囲の関節包や靭帯を硬化させ、動かすたびに違和感やつまり感を引き起こします。 -
自律神経や血流の影響
股関節周囲の血流が悪化すると、筋肉や関節の回復が遅れ、慢性的なつまり感や疲労感を感じやすくなります。
股関節のつまりが引き起こす体への影響
股関節の動きが悪いと、体全体にさまざまな悪影響が現れます。
-
腰痛・膝痛:股関節の可動域が狭いと、腰や膝で体重を支えようとして負担が集中。
-
姿勢の崩れ:前傾や反り腰、O脚やX脚などの姿勢不良につながります。
-
疲れやすさ・だるさ:血流やリンパの流れが滞り、体の回復力が低下。
-
歩行の不安定感:バランスが悪くなるため、転倒のリスクが上がります。
これらは「ただの股関節の硬さ」と思われがちですが、放置すると慢性的な体の不調やケガに直結します。
自宅でできるセルフチェックと簡単ケア
まずは股関節の状態を知ることが重要です。以下のチェックで確認できます。
-
足を前後に動かすと左右差がある
-
立ったまま片足を持ち上げるとぐらつく
-
座って足を開くと硬さや痛みを感じる
簡単ストレッチ
-
股関節回し:椅子に座り片足を前に出し、膝をゆっくり回す
-
お尻ストレッチ:仰向けで膝を抱え、片足を胸に引き寄せる
-
内ももストレッチ:脚を開いて前屈、呼吸に合わせてゆっくり伸ばす
毎日5分〜10分行うだけでも可動域改善の効果があります。
専門施術での改善 ― ちゅ楽のアプローチ
自宅ケアだけでは改善が難しい場合もあります。
青葉台「ちゅ楽」では、股関節周囲の筋膜・関節・神経にアプローチする施術が可能です。
-
リリース整体:筋膜の癒着を解消し、股関節の動きをスムーズに
-
ボディケア:大腿・臀筋・内転筋をほぐして血流改善
-
アロマトリートメント:血流・リンパ促進で疲労回復
-
インディバ:深部まで温めて柔軟性向上と痛み軽減
これらを組み合わせることで、ただ股関節を動かすだけでは得られない「体の軽さ」や「動きやすさ」を実感できます。
まとめ
股関節のつまりは、日常生活に潜む小さな違和感ですが、放置すると体全体の不調につながります。
セルフケアで動きを確認しつつ、専門施術を取り入れることで、腰・膝・姿勢・疲労感の改善が可能です。
今、股関節の違和感を感じている方は、ちゅ楽の施術で体の変化を実感してみてください。
動きやすくなることで、毎日の生活の質がぐっと高まります。
(ちゅ楽) 2025年11月23日 07:00
首の痛み ― その不調、単なる肩こりじゃないかも?原因と改善法を徹底解説

「朝起きたら首が痛い」「長時間のデスクワークで首がこる」「肩や背中まで重くなる」
首の不調は多くの人が経験する悩みですが、放置すると慢性的な痛みや頭痛、自律神経の乱れまで引き起こすことがあります。
今回は、首の痛みの原因、体への影響、そして自宅でできるセルフケアや専門的な施術について、詳しく解説します。
■ 首の痛みの主な原因
首の痛みは一つの原因で起こることは少なく、多くの場合は複数の要素が絡み合っています。
1. 姿勢の崩れ
デスクワークやスマホの長時間使用で首が前に出る「ストレートネック」は、
首の自然なカーブを失わせ、筋肉に負担をかけます。
前傾姿勢が続くと、僧帽筋や胸鎖乳突筋などが緊張し、首や肩の痛み、頭痛の原因になります。
2. 筋肉の疲労・こわばり
首周りの筋肉が緊張すると、血流が悪くなり、乳酸や疲労物質が溜まります。
これが慢性的な痛みや重だるさの原因となります。
3. 神経の圧迫
首の骨(頸椎)がずれたり、椎間板が狭くなったりすると、
神経が圧迫され手や腕のしびれや冷えを伴うことがあります。
症状が強い場合は、整形外科や専門施術の受診が必要です。
4. 自律神経の影響
首周りの筋肉が硬くなると、交感神経が優位になりやすく、慢性的な緊張状態に。
その結果、肩こり・頭痛・眠りの質低下・疲労感など、全身の不調につながります。
■ 首の痛みが体に及ぼす影響
-
肩こり・背中の張り
首が硬いと、肩や背中の筋肉に負担が移り、慢性的なコリを生む。 -
自律神経の乱れ
首の筋肉と神経の関係は密接で、硬さや痛みが交感神経を刺激し、眠りにくさや疲労感につながる。
■ セルフチェック・セルフケア
首の痛みセルフチェック
-
首を前に倒すと痛い
-
回すと引っかかる感じがある
-
肩や腕にしびれ・だるさがある
-
長時間のデスクワーク後に痛みが強くなる
これらの症状がある場合は、日常生活の見直しや早めのケアが重要です。
自宅でできるセルフケア
-
首ストレッチ
ゆっくりと頭を左右に倒す。痛みが出ない範囲で1日数回。 -
肩甲骨まわりの運動
肩を回す、肩甲骨を寄せる動作で首・肩の緊張を緩和。 -
温め
首の血流を促すため、蒸しタオルや入浴で温める。 -
姿勢の見直し
デスクワークではモニターの高さを目線に合わせ、スマホは目の高さで操作。
■ 専門施術での改善
青葉台「ちゅ楽」では、首の痛みに対して以下の施術をおすすめしています。
1. リリース整体
筋膜・関節・神経のバランスを整え、首の可動域を改善します。慢性的な痛みやコリを根本からケア。
2. ボディケア
肩や背中の筋肉を丁寧にほぐし、首への負担を減らします。
3. 脳疲労ケア(ヘッドケア)
首や頭の緊張を解き、血流・リンパの流れを改善。
副交感神経を優位にすることで、心身ともにリラックス。
4. インディバ
高周波温熱で首の深部まで温め、筋肉や関節の柔軟性を向上。痛みの軽減、疲労回復に効果的です。
■ まとめ
首の痛みは、日常の姿勢や筋肉のこわばり、自律神経の乱れなど複合的な要因で生じます。
放置すると慢性化や頭痛、肩こり、しびれなど全身の不調につながるため、早めのケアが重要です。
青葉台「ちゅ楽」では、痛みの原因に合わせたリリース整体・ボディケア・脳疲労ケア・インディバなど
多角的アプローチで、首の痛みを根本から改善します。
セルフケアと組み合わせることで、再発予防や疲れにくい体づくりが可能です。
首の痛みに悩む方は、ぜひ一度「ちゅ楽」の施術で体の変化を体感してみてください。
痛みが軽くなるだけでなく、肩や背中、頭の重さもスッキリし、毎日の生活が快適になります。
(ちゅ楽) 2025年11月22日 07:44